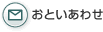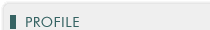志賀泉の「新明解国語辞典小説」
と
とうしみとんぼ
2010/06/04
とうしみとんぼ【灯心とんぼ】
〔「とうしみ」は「とうしん」の雅語形〕トンボの一種。からだは細くて緑色。羽が弱い。イトトンボ。とうすみとんぼ。
携帯電話が手から滑り落ちた。足下に落ちたそれを拾おうと、慌てて腰をかがめた拍子に、つま先で蹴ってしまった。
橋の上でのこと。集団下校の帰りだった。
携帯電話は菜々子の指先から逃げ、菜々子の前を歩く、集団下校の仲間の足下へと滑り込んだ。誰かの足が携帯電話を蹴り、別の誰かがさらに蹴った。携帯電話は彼らの足下から弾き出され、ガードレールの下をくぐって川に落ちていった。
またたく間の出来事だった。声を上げるひまもなかった。
偶然? 誰も気づかなかったの? うそ。わざとだ。菜々子は仲間の背中をにらんだ。みんな黙々と歩いているが、背中で揺れるランドセルがくすくす笑っていた。
携帯電話はコンクリートの川底に沈み、水色のボディが光の屈折でゆらゆらしていた。
菜々子の心が、ポキリと折れた。
やっぱり、山村留学に行こう。折れた心で、そう決めていた。
菜々子の小学校では、生徒は学校に携帯電話を持ち込んではいけない決まりだ。菜々子は特別に許可をもらい、携帯電話を肌身離さず持ち歩いていた。
菜々子は五年生だ。お母さんは首都高速道路で交通事故に遭い、それからずっと、意識をなくして入院している。いま、菜々子はお父さんとふたり暮らしだ。緊急の場合にはすぐさま連絡がとれるようにと、先生が配慮してくれたのだが、クラスメイトの中には特別扱いをやっかむ者もいた。
だから、めったに人前では携帯電話を使わない。さっきは自分の携帯電話と同じ着信音が聞こえて、もしやと思い手に取ったらば、自分のでない、たまたますれ違った大人の携帯電話だった。ほっとして、手がゆるんだ。とたん、するっ。かしゃん。
電話の音に敏感になっていた。お母さんの事故を最初にしらせた、家の電話の呼び出し音が耳に甦るからだ。トラウマになっているのかな、と思う。静まり返った教室でも、着信音を空耳に聞いた。そっと携帯電話を手にして、先生に注意された。クラスメイトの視線が痛かった。消え入りたいくらい、苦しかった。
お母さんの事故以来、心が不安定だ。お父さんは毎日仕事帰りに病院に寄って、菜々子の面倒を見きれない。「五年生になったら一年間、伊豆の山村に留学してみたらどうか」とお父さんが言い出したのは去年の十一月だった。
事故から半年が過ぎていた。回復の見込みはなく、かといって、容体が急変する怖れも遠退いていた。もしものことが仮に起きても、半日で病院に駆けつけられる距離だ。
イヤ。絶対イヤ。菜々子は拒否した。お母さんの近くにいたかった。田舎暮らしなんてしたくなかった。なにより、お父さんに厄介払いされるみたいで怖かった。頑固に拒みとおして、五年に進級した。
なのに、川に沈んだ携帯電話を橋の上から見下ろした、そのとたん、あっけなく心が折れた。ぽきん、という音まで聞こえた。
それが四月の終わりのことだ。早々に手続きをすませ、五月の連休明け、菜々子の山村留学は始まった。伊豆半島の付け根にある静かな山里だ。
菜々子は区長さんの家にホームステイした。農家で、広い庭と長い縁側があった。子供の日は過ぎたのに、鯉のぼりが庭に泳いでいた。緋鯉が真鯉の上にあった。菜々子の肩からどっと力が抜けた。力が抜けすぎて、理由のわからないまま、涙がぼろぼろ零れた。
「菜々子ちゃん、スイカお願い」とおばさんに言いつけられ、菜々子は「はあい」と返事し、サンダルをつっかけ裏庭に出た。井戸にスイカを冷やしてある。
屋根があって、滑車がついて、日本昔ばなしみたいな井戸だ。ここで野菜を洗ったり冷やしたりする。屋根には苔が生え、草が伸び、大きな穴が開いたままになっている。
蓋をのけると、暗い水のにおいがする。吸い込むと肺の中まで暗く染まりそうな、重いにおい。慣れない頃は井戸に落ちてしまいそうで怖かった。覗き込むと、すっと、頭が重くなる。井戸の底は地球の中心に近いぶん、重力も強いのではないか。
いまは平気だ。井戸に引き込まれそうな力はいまも感じる。ただ、重力にあらがうだけの踏ん張りが、菜々子の足腰についたのだ。
井桁(いげた)に手をかけ、覗き込む。空の光が、屋根の穴をとおり抜け、暗い水面に円く差し込む。円い光の中心に浮いた黒い玉が、スイカだ。スイカに菜々子の影が重なる。
頼りない影。自分の影が自分でないみたいな。井戸は深くて、お母さんの眠りも、これくらい深いのではないかと考える。事故後しばらくは、呼びかければ脳波計が反応した。見た目に変化はなくても、声はちゃんと届いていた。それがひと月もすると、声が届かなくなった。眠りが深くなったのだ。てのひらをペンでつつけばわずかに反応する。反応がなくなれば脳死だと、お医者さんは言った。
脳死? 脳死というのは、眠りの底が抜けるということ。
よく見れば、井戸の底の水面はかすかに揺れている。井戸水は流れている。おじさんがそう教えてくれた。井戸水が流れる? ああ、地下水が井戸をとおり抜けていくのさ。
スイカは、ロープを結わえた笊(ざる)に載せてあるので、ロープを手繰り寄せれば引き上げられる。井戸で冷やしたスイカは重くなる。これは菜々子の発見だった。
濡れたスイカを抱え、井戸端にしゃがむ。風が吹いて竹藪がざわめく。蝉の声は遠い。
いつの間にか、井桁に蜻蛉(とんぼ)がとまっていた。
「あ、イトトンボ」菜々子は呟いた。
井戸水のにおいに誘われたのだろう。蜻蛉だって、よく見ればそれなりに凶暴な面構えなのに、これにはそれがない。カゲロウのようにはかなくて、こわれやすく、消え入りそうで。なにを食べるのだろう。水だけ飲んで生きていそうだ。全身が神経の糸でできているような、ささやかな生き物だ。すっと飛び立てば、すぐ空中にまぎれて目で追えなくなる。目に見える世界と見えない世界の境を、イトトンボはすずやかに飛ぶ。
五年生は、菜々子をふくめて四人いた。六年生は二人いて、ひとつの教室で一人の先生が授業を同時進行させた。勉強がはかどらないだろうと思ったら、そうでもなかった。むしろ都会の学校より授業の中身が濃くて、びっくりした。
教科書の授業のほかに、五年生と六年生は自然研究という授業があった。留学の子と地元の子が二人ひと組になって、身の回りの自然からテーマを選び一年かけて研究する。
菜々子は条太郎という男子と組んだ。男子と組むだけでも嫌だったが、条太郎が研究していたのはクモだった。空の雲? ううん、虫の蜘蛛(くも)。げっ。
ヤだ、ぜったいヤだ。ヤダって言ったって俺もうやっちゃってるし、おまえと組むの決めたの先生だし。おまえなんて呼ばないでよ。
条太郎は一人で研究をしていたのだ。後から来た転校生が女子だからって、有無は言わせなかった。
「じゃあ、俺は蜘蛛を調べるから、おまえ網の担当な。それでいいだろ」
「網? 蜘蛛の巣?」
「巣じゃなくて網。ウェブ。蜘蛛の巣なんて言うのは素人だ」
「素人でいいけど」
「蜘蛛はかしこいんだよ。たとえばさ、なんで蜘蛛は自分の糸に足をくっつけないで歩けるか、おまえ知ってる?」
「おまえなんて呼ばないでよ」
「ネバネバがあるのは横糸だけで、縦糸にはないから。蜘蛛は縦糸だけ伝って歩くんだ」
毎週金曜日の午後は、自然研究の時間だ。条太郎と菜々子は蜘蛛を探して神社やお寺を歩いた。蜘蛛がいそうだとにらむと、条太郎は他人の家の庭でも平気で入った。
菜々子は条太郎に、蜘蛛の網を標本にとる方法を教わった。これと決めたら、白のラッカーを網に吹きかけて見やすくし、黒い台紙に水糊を塗って、ぺたんと貼りつける。一発勝負なので緊張した。失敗すると糸が切れたり、貼りつける瞬間に網がずれたりで、台無しになる。うまくいけば、標本は美しかった。蜘蛛の網はそれぞれ個性的で、機能的で、ある意味、知的だった。
条太郎は種類ごとに分けて虫かごに蜘蛛を飼っていた。蜘蛛を飼うなんて、どういう神経だろう。条太郎の虫かごを菜々子はなるべく見ないようにした。網をきれいだと思えるようになっても、蜘蛛そのものはやっぱり怖い。網の中心でじっとしているならまだいいけど、動き出すとぞっとする。背筋に寒気が走る。
いちど、条太郎が蜘蛛の糸を指先でつまみ、小さな蜘蛛をぶら下げたまま菜々子の鼻先に突きつけたときは、手にした図鑑で思いきり殴ってしまった。「冗談だよ冗談」と言いながら条太郎は鼻を押さえたが、てのひらの隙間から見る見る鼻血が流れ出した。
それからしばらくは、教室にいても、お互い口をきかなかった。
仲直りはちょっとしたきっかけだった。
庭に立っていたら、ひと筋の糸が微風に乗ってふうわりと目の前を流れていったのだ。目に見えない細さだが、光の当たり具合で部分的に白く光ったり消えたりした。
あっ、蜘蛛が糸を飛ばしてるんだ。
心が躍り、菜々子は条太郎の家に電話をかけた。条太郎は自転車を飛ばしてやってきた。家のひさしから庭のモチノキにかけて、糸はつながっていた。七、八メートルはある。糸を伝う蜘蛛を見て、条太郎は「オニグモだ」と断定した。茶色くて大きな蜘蛛だ。菜々子はスケッチブックを開き、網を作る手順に即して何枚も写生していった。
オニグモは急き立てられてでもいるみたいにそそくさ働いた。かなり大きな網で、人間にたとえれば、校庭いっぱいに網を広げるのに等しい。
「あんまり大きくし過ぎて、不安にならないのかな」
菜々子はオニグモの気持ちになった。蜘蛛に感情移入したのは初めてだ。
「いっぱい糸を使えば、それだけたくさん獲物を仕留められるから」条太郎は言った。
けれど、菜々子が感じた不安はそういうことではなかった。
オニグモは空そのものに網を張っているふうに見えた。空の途方もない広さに見合うだけの網を張ろうとして、網を大きくすればするほど、自分はちっぽけな存在になり、身の置きどころをなくしてしまうのではないか。空の一角で、光や風に体をさらして待つだけの身になり、寂しさに押し潰されそうにならないのだろうか。
自転車のスポークの形に似た、放射状の縦糸を張り終わり、オニグモはその中心から渦を描くように横糸を張りめぐらしていく。仕上がりつつある網の向こうで、空は赤みを帯びていった。山の端に積み重なって湧き立つ雲が、夕陽をはらんで燃え上がる。夕陽はスケッチブックを照らし、条太郎もオニグモも照らした。条太郎の顔を、きれいだと菜々子は思った。整った顔立ちだとは認めていたが、きれいだと思ったのは初めてだった。
「おまえ、蜘蛛を気持ち悪いと思ってるだろ」条太郎は言った。「蜘蛛は弱い生き物なんだ。弱くて臆病なんだ。網っていうのはさ、弱くて臆病なやつが生き延びてくために発明した、知恵の結晶なんだ」それから、「だから網は美しいんだ」と付け加えた。
美しい、なんて言葉を照れもせず条太郎が口にしたから、菜々子はびっくりした。
条太郎の目は澄んでいた。見るものと見られるものがひとつになっていた。蜘蛛の網の中心に条太郎はいた。そこがいまの条太郎の、世界の中心だった。
すっかり日が落ちてあたりが暗くなった頃、網は完成した。条太郎は菜々子がホームステイしている家で、夕飯を食べて帰っていった。
夜更けに目覚めた。蚊帳の中で。蚊帳は蜘蛛の網を思わせる。菜々子は、夜闇の庭に広がる網を思った。いまも網の中心で息をひそめているはずのオニグモを思った。
菜々子は夢想した。網の中心にいるオニグモはお母さんだ。お母さんが夜空に網を広げている。菜々子は網の中心から遠く離れ、端っこで暴れる羽虫だった。ワタシハココニイル。いくらばたついても、お母さんは気づかない。ワタシハココニイル。必死で羽を震わせても、震動の波は網に吸収され、深く眠ったお母さんを揺り動かせない。
そんな夢想をして、菜々子は泣いた。
菜々子が初潮を迎えたのは夏休みの四日前だった。
予感はあった。少し前から下腹が重苦しかった。生理のことは教わっていたので、それかな、と感じながら、認めるのが怖くて予感を遠ざけていた。来なければいいのに。ずうっと来なければいいのに。なのに、とうとう来た。午後の時間。よりによって体育の授業中に。太陽が暗くなった。黒い太陽が校庭から熱を奪っていった。汗が冷えて、菜々子はへたり込んだ。
保健室には生理用品も替えの下着もあった。こんなの、なんでもないことなんだよ、というように。ブラウスとスカートに着替え、ベッドに横になって校庭の声を聞いてると、世界中のなにもかもが自分から遠ざかっていくようで、せつなかった。
生理になんてなりたくなかった。子供のままでいたかった。妊娠できる体になったのかと思うと、体の中が暗くなった。自分の体がやましいものに感じられた。
お母さんを思った。これでお母さんと同じだ。自分の体の暗さが、お母さんの眠りの暗さにつながっているように思えた。
午後の時間をずっと、ベッドで過ごした。放課後になっても起き上がれなった。ベッドは白いカーテンで人の目から隠されている。カーテン越しに、膝をすりむいた下級生の泣き声を聞いた。すでに初潮を体験した上級生が訪ねてきて、短い話をして帰っていった。それ以外は放っておかれた。廊下を走る音がした。たてぶえが鳴っていた。いろんな音が遠く近く聞こえ、身の置きどころがなくなりそうで、つらかった。
風が吹いて、窓のカーテンがふくらんだ。
蜻蛉がすうっと飛んできて、窓の敷居に止まった。あっ、イトトンボ。
細い尻尾を、ぴんと伸ばして、アンテナみたいに。菜々子はそっと指を伸ばした。イトトンボは糸を引くような軌跡を残して、窓の外に飛び去っていった。
菜々子は上履きをはいて、窓から外に下り立った。
裏庭は柵のないまま裏山につながっている。痛みの残る下腹を片手で押さえながら小径を歩き、菜々子は裏山へ入っていった。誰にも会いたくない。家に帰りたくない。森の奥深く分け入って、自分を消してしまいたかった。
怖いくらい旺盛に茂った枝葉が重なり合って光をさえぎり、森はほの暗い。歩めば土の陰気さが足下からわきたつ。自然がやさしいなんて、うそだ。やさしい自然なんて人の作り物なのだ。本物の自然はさびしい。ひとりぽっち、自然に包まれていると、心が押し潰されそうになる。
途中から道をそれ、岩を伝い、渓流に下りた。流れに足をひたすと、水の冷たさが下腹に響いた。そういえば、携帯電話、東京の川に落としたきりだ。あの携帯電話、いまも沈んだままだろうか。川底で、誰かからの電波を受け取ったりしないだろうか。
ナナコ。ナナコ。ナナコ。ナナコ。ドコニイルノ?
流れに逆らい、上流を目指した。歩くにつれて渓流の表情が険しくなり、水のにおいが濃くなっていった。水音は鋭さをまし、菜々子の体を包み、削いでいく。このまま肉を削がれて細く細く細くとがり、イトトンボになりたかった。あんなふうに、はかない体になれば、体ぜんたい受け身になって、遠い電波をキャッチできるかもしれない。
渓流を登りつめると、いきなり視界がひらけた。目の前に滝があった。森の高みから溢れ出す水が、轟音を立てて落ちていく。飛沫(しぶき)が風に乗り、菜々子の顔を濡らす。菜々子はかたわらの岩に手をつき、細い息を長々と吐いた。
人の気配がして顔を上げた。なぜか、条太郎がいた。Tシャツが濡れて肌にぴったり張りついていた。滝が波紋を広げる滝壺の水辺で、腰まで水に浸かり、菜々子を見ていた。
安堵と恥ずかしさで、心臓がどきどきした。平然としている条太郎が憎らしかった。
「なにしてんのよ」菜々子は尋ねた。
「ミズグモ探してんだよ」条太郎はぶっきらぼうに言った。いつもと調子が違う。「ミズグモは水面すれすれに網を張って川虫を捕まえるんだ」
「条太郎君はきっと、前世で蜘蛛だったんだよ」
「おまえこそ、なにしてんだ?」
「おまえなんて呼ばないで」
「顔色悪いぞ。寝てなくていいのかよ。生理になったんだろ」
さっと、血の気が引いた。
「うっせえ、ばか」石をひろい投げつけた。小石なんかじゃない。
「うわ、当たる。マジあぶねえ。心配してやってんじゃねえかよ。うわっ。だから当たるって、なに怒ってんだよ。うわっ。止めろって」
「うっせえんだよ。この非常識。無神経。クモバカ。田舎者!」
一瞬の沈黙。条太郎はきょとんとして、それから、
「誰が田舎者だ!」突然、キレた。
肩をいからせた条太郎は急に男臭くなった。ケモノの形相を剥き出しに、波を蹴立てて突進してきた。
怖かった。仕返しされる、というだけでなくて、性的な意味で、襲われる、と思った。こんなふうに条太郎を感じたのは初めてだ。
菜々子は逃げた。滝壺の水辺を走り、足を滑らせて深みにはまった。水底につま先が届かなかった。泳げないわけではなかったが、叫ぼうとして思いきり水を飲み、パニックになった。波立つ水面の向こうに条太郎が見えた。飛び込んできた条太郎にしがみついた。あまり強く抱きしめたものだから、二人からまったまま、水底に沈んだ。水底の暗さが、目に残った。
気がつけば、頭からタオルをかぶり、膝を抱えて震えていた。
条太郎はすぐそばにいた。
夕焼けを映す滝壺の上を、たくさんの虫が飛び交っていた。
「さっき、家に電話した。もうすぐ迎えがくるから。俺のオヤジ、力持ちだから、おぶさって帰ればいい」
条太郎はやさしかった。
「ケータイ? 持ってたんだ」
「森に入るときは、まんがいちってことがあるから、オヤジのケータイを借りる」
「圏外じゃないんだ、ここ」
「県外? ここ、静岡県だよ」
「そのケンガイじゃない」
ばか、と呟いて、おかしくなった。くつくつ、腹を震わせて笑った。
「なんだよ、なに笑ってんだよ」条太郎はわかっていない。「変なやつ」
森の奥から夕闇は押し寄せ、翳りゆく滝壺に、滝ばかりが白く浮き立つ。
目の前の岩肌にイトトンボがとまっていた。ウエハースのように薄い羽が、茜色の空を映していた。じっとして、自分の弱さの中に、意識を細く研ぎ澄ましている。
緑色の細い尻尾をぴんと上向ける。その先が、ぽっと、青く灯った。アルコールランプの炎に似た、淡い光だった。