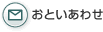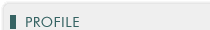志賀泉の「新明解国語辞典小説」
て
てのひら
2010/05/16
てのひら【掌】
〔「手の平」の意〕手首から先の、物を握る時の内面の面。たなごころ。
君。
そう、これを読んでいる君だ。
俺は、君が誰だかわからない。わかっているのは、君が二十歳くらいの女性だってことくらい。名前も知らない。どんな声でしゃべるのか、知らない。好きな色は? 好きな食い物は? 好きな音楽は?
この文章は特定の個人、つまり君への手紙だ。けれど、君以外の人は読んでも仕方がないとか、無意味だとかいうのではない。君以外の人にとってのこれは、一個の物語だ。読んでほしい。読んでくれ。そしてなにかを感じ取ってくれたら、俺はうれしい。
この文章が君に届くかわからない。届かない確率のほうが圧倒的に高い。でも書く。書きたいから書く。なにかの奇跡でこいつが君に届くことがあるかもしれない。そしたら会ってくれ。話がしたい。方法はあとで記す。もちろんこれは罠なんかじゃない。君をはめるつもりはない。純粋に、会いたいだけだ。
君と俺は深夜のコンビニで出会った。覚えているはずだ。川崎と横浜を結ぶ産業道路から、北に折れて鶴見駅に向かう道の、十字路の角にあるコンビニエンスストア。ほら、対角線にエッソのガソリンスタンドがある、あの店。十字路に横断歩道はなく歩道橋だけがあって、その歩道橋の階段はぐるっと螺旋形になっていて、でも歩道橋を無視して道を横切る人は多いから、車にはねられて天国に直行した人の慰霊の花束が橋脚の真下にある。雨が降るとホームレスがやってきて花束に添い寝する。その歩道橋の目と鼻の先にあるコンビニ。俺はそこで働いている。週四回、夜の十時から翌朝の七時まで。
全国のコンビニの総数は四万店を突破した。去年一年間のコンビニ強盗の件数はおよそ九百件。四十四分の一の割合で被害に遭っている計算だ。数字だけ見るとまだまだこんなもんかと思えるけど、事件は都市部に集中してるし、商店街から離れた殺風景な場所にある店となると、事件の起きる確率はぐんと高くなる。つまりだ、俺が働いている店は、じゅうぶんヤバイわけだ。
働きはじめてすぐ、強盗対策の講習を受けた。ほら、蛍光塗料を塗ったカラーボールを犯人の背中にぶつけるってやつ。でも、そんなの実際には屁の役にも立たない。強盗がきたらさっさとお金を渡すべし。下手な抵抗は身を滅ぼす。これが現場の共通意見だ。俺もそう思う。
「去年の夏だっけ、暴走族くさいのが集団でやって来てさ、あからさまに行動がおかしいわけ。見え見えで万引きしてんの。あれ、俺なめられてんのって、むかついてさ、『おいこら』って注意したら、襟首つかまれてボコボコにされて、外に引きずり出された。まじやばかったよ。あいつら、車のトランク開けてたもん。もう少しで拉致されて山に埋められるとこだった」
これは相棒のアルバイトから聞いた実話だ。彼の体験から導き出される教訓は、「やばそうな奴には近づくな」だ。
どうしてこんな話をしてるかって? つまりだ、俺も日頃から犯罪に対する心構えは持っていたってことだ。犯人の目的がはっきりしていれば対処方はある。しかし君は? わからない。君の目的はなんだったんだ?
あの夜の相棒はお世辞にも仕事熱心と言えず、先輩格であるのをいいことに少年ジャンプやマガジンが届けば真っ先にひっつかんでレジの奥に引っこみ読了するまで腰が上がらないという最低の奴だった。
午前二時過ぎのことだ。相棒はレジの奥、防犯カメラの真下の、つまり死角になる定位置で手足を縮めて返品予定の雑誌を読みふけっていた。店内に客はいなかった。俺は店の奥で商品棚の整理をしていた。自動ドアが開いた。チャイムが鳴った。そして若い女、つまり君が入ってきた。
俺は防犯ミラーで君を見ていた。長い黒髪。臙脂色のブラウスに黒のオーバーコート。ジーパンにパンプス。別に変わったところはなかった。近所の人がコートを引っ掛けて買い物にきた、という感じだ。君は雑誌棚の前でいちど立ち止まり、腕を組みざっと棚を見ただけでドリンクのコーナーに移動し、そのまま俺の後ろを通り過ぎてお菓子のコーナーの前で足を止めた。チョコレートを選んでいるふうだった。店内のBGMはコンクリート・バッファローズの「千年の森」だった。覚えてる。俺はこの曲が好きで、こいつが流れるとつい鼻歌が出てしまうんだ。
ふと気づくと、君はレジカウンターの前にいた。相棒はいない。君は店員を呼ばず、店員を探してきょろきょろもせず、静かに立っていた。ほっといたら朝まで立っていそうな後ろ姿だった。あの野郎またさぼってやがる。俺は思わず舌打ちした。その音が聞こえたのか、君はゆっくりとふり返り、俺と目を合わせると軽く頭を下げた。「おいそがしいところまことにすいませんがレジをお願いします」とでも言いそうな上品な雰囲気だったから、俺は恐縮して小走りでカウンターに戻った。
カウンターには板チョコが一枚。深夜の買い物に板チョコが一枚、というのはあまりない。でも訝しがるほどのことではないので、俺はスキャナーでバーコードを読み「百六十円になります」と言った。君はポーチから財布を取り出した。小銭を出すのに少々手間取っている様子だった。俺は右手を宙に浮かして待った。すると君は、左手を俺の手に裏から重ねるように添え、右手で五百円玉を渡そうとした。
そのとき不審に思わなかったのか? 警察に何度も聞かれた質問だ。
「いえ、別に」俺は答えた。
「客がお金を払うにしては、不自然な仕草と思わなかったか?」
「店員がお釣りを渡すときにはよくやります。小銭を落とさないように」
「しかし、客のほうがそうすることはないだろう」
「あまりないですね」
「あまりない? まったくない?」
「まったく」
「それでも不自然とは感じなかったわけだ」
あんまり根ほり葉ほり尋ねるからうんざりした。まるで犯人の取り調べみたいだった。
お客さんの仕草を自然とみるか不自然とみるかは、動作や態度より、その人が醸し出す雰囲気に左右される。俺は君の仕草を自然に受け入れた。そう、ここまでは。
君は俺の右手に五百円玉を置いた。垂直に。そして手前にすっと引いた。てのひらの皮膚がぱっくり割れた。痛みは感じなかった。「あれ?」とだけ思った。「あれれ?」
見る間に血があふれ出てきた。痛みはあとから追いかけてきた。引っ込めようとした俺の手首を君は握った。激痛がてのひらから腕の表面を走り頭頂に達した。「いてえ!」俺は叫んだ。髪の毛が総立ちになった。なにが起きたのか、まったく見当がつかなかった。
真っ赤になった俺のてのひらを君は右手で握った。ふたりのてのひらの間から鮮血はぽたぽた滴った。振りほどこうにも腕がしびれて力がはいらない。それでも、必死でぐんと腕を引くと、君はがくんとカウンターの上に前のめりになった。
君。
君はあのときなにを考えていた?
俺は君の目を直視していた。君も俺の目を直視していた。
もし、君が凶暴な目で俺をにらんでいたら、もしくは錯乱した目を泳がせていたら、俺は恐怖のあまり自由な左手で君を殴っていたかもしれない。あるいは鋏で君の手を突いたかもしれない。けれど、どう言えばいいんだろう。君の目に怒りや怯えはなかった。俺になにかを訴えたがっているように見えた。この非常事態になに悠長なこと言ってんだって、人は思うだろう。でも、たしかに言えるのは、君の目は精神異常者や薬物中毒者のような平板な目ではなかったこと。ずっと奥の深い目をしていたことなんだ。
だから俺は、頭のどこかでは冷静でいられた。全面的には君を拒絶できなかった。これはなにか理由のあることなんだと考えていた。
ねえ君、これだけは教えてくれ。君は俺を狙っていたのか? たまたま俺がレジに立ったから俺を傷つけただけで、相棒がレジに立ったらやっぱり同じことをしていたのか?
考えすぎだろうか。俺はただの自意識過剰なんだろうか。
俺の声を聞いて相棒が裏の倉庫から飛んできた。同時に君は手を放した。俺がよろけて相棒にぶつかった隙に、君は板チョコをつかんで逃げていった。レジが開いていたので、相棒は強盗と勘違いした。
「どろぼう!」と見当外れのことを叫んだ。「どろぼう、どろぼう!」
相棒はカラーボールを手に君を追いかけ表に飛び出した。投げたボールは別人の顔面に当たり、事態はややこしくなった。でもそれは君にとってラッキーだった。そいつが相棒に食ってかかっている間に君はどこかへ逃げていったのだから。
五百円玉がカウンターに残されていた。俺のてのひらを切り裂いた凶器。君は、どういうつもりであんな細工をしたんだ? カッターの刃を、硬貨の端からほんの少しはみ出る具合に、セロテープで貼って。
それともうひとつ、君に言いたいことがある。俺はまだ、お釣りの三百四十円を君に返してない。
君が逃げた後、俺は血まみれのカウンターの上で、右手をおさえて痛みをこらえながら思い出したんだ。「あ、お釣り渡してねえ」って。
俺自身のことを書く。
二十六歳。出身は新潟県。横浜市鶴見区在住。ミュージシャン。履歴書の職業欄に「ロックンローラー」と書いて笑われたことがある。ロックンローラーとは生き方であって職業ではなかったんだ。
バンドを組んで横浜にある「ロドリゲス」っていう店を拠点にライブ活動をしていた。「していた」って過去形なのは、過去の話だからだ。ドラムを担当していた。わかると思うけど、俺の手は俺の商売道具だった。
包帯を巻いてる間、ドラムを叩けなかった。でも、さいわい傷は浅かったから、傷がふさがればちゃんと復活できたはずだ。
けれど、ライブハウスのスケジュールはびっちり決まってたからバンドの連中は焦った。どっかからドラマーを探してきて急遽メンバーに加えた。俺が復帰するまでの代役という話だったが、怪しいものだ。そいつ、埋もれた逸材だった。初めてそいつのドラムを聴いたとき、顔から血の気が引いたね。冷や汗が背中にどっと流れた。そんで悟った。「あ、俺もう終わりだ」って。
俺は元々ベース奏者だったんだ。それがあの連中とバンドを組んだとき、ドラマーがいなかったので俺がやることになった。正直、不本意だった。でも俺は文句もたれずドラムに打ち込んだよ。必死で練習した。そこそこは上手くなった。けど、魂じゃ乗り越えられない壁ってどうしてもある。もしかして俺、バンドの足引っ張ってんのかもってひそかに不安だった。でも、俺だって好きでドラマーに転向したわけじゃないから、そこんところはみんな理解してくれてた。なんだかんだいって、うまくやってこれたんだよ。
そう、あの事件までは。
日に日に空気が悪くなっていった。みんな、俺への態度がよそよそしくなった。そりゃあ、辞めてくれって口に出す奴はいなかった。けど俺も馬鹿じゃないからね。誰も俺の傷が治るのを望まなかった。それは肌で感じた。飲み会でも、畳の上に右手を置けなかったくらいだ。うっかり置こうものなら、誰かがうっかりのふりで俺の手を踏んづけるか物を落としそうで危険だった。
まさかと思うだろ。でも音楽やる人間ってそういうものだ。チャンスとみたら平気で人を裏切る。のし上がるためなら残酷になる。そうでなくちゃ駄目なんだ。だから、奴らの態度はある意味正解。奴らだけじゃなしに、ファンも、ライブのオーナーも、俺の復帰を望まなかったんだから。
傷が癒えても、しばらく包帯を外せなかった。結局、「後遺症が残りそうなんで」って嘘ついて自分から抜けたよ。「ああ、そりゃ残念だ」って、うれしそうにしてる仲間が悪魔に見えた。
あ、いや、君のせいだって責めてるわけじゃない。こうなったほうがバンドのためでもあり俺のためでもあったんだ。ひとりになったって俺はロックンローラーだ。俺はいまストリートに出ている。アコースティックギターを弾いて自作の歌を歌ってる。敗北でも転落でもない。いわば後ろ向きで前進。俺は自分の原点に戻ったんだ。
その他にも、言っておきたいことがある。
警察はまずコンビニ強盗の線を考えた。君が俺の手を握って放さなかったのは、俺の頸動脈も切って致命傷を負わせ、レジの現金を奪う計画だったんじゃないかという推理だ。でも、強盗にしちゃ変だ。だいいち、若い女性がひとりで強盗なんてあんまり聞かない。しかも素顔まるだしで。逃走を考えたらパンプスは履かないだろう、ふつうは。
それに、もし本当に君が俺の手首も切るつもりだったら、さっさと切ったはずだ。でも君はしなかった。レジの現金には目もくれなかった。
二番目に警察は、怨恨の線を考えた。犯人に見覚えはないか、女性に恨まれる覚えはないか、しつこく聞かれた。ない、と俺は言い切れなかった。店そのものへの復讐という線も考えられた。過去につかまえた万引き犯、売り上げをちょろまかすなどの罪でクビになった元アルバイトの記録を徹底的に調べた。
俺は、防犯カメラに残された君の画像と、過去数年間でしょっぴいた万引き犯や問題行動のアルバイトの画像を見比べた。なにせ膨大な数だったから半日がかりだった。万引き犯の画像をまとめて見ていくと、興味深い共通点があることに俺は気づいたが、それは横に置く。いま問題なのは、過去の万引き犯やクビになったアルバイトに君らしき人物は見当たらなかったことだ。
すると警察は個人的怨恨の線に戻り、俺の女性関係を探った。高校時代までさかのぼって、痛くない腹をさんざん探られた。なにせ俺はミュージシャンだから、警察官だって先入観で俺を見る。まったく、俺が取り調べを受けてるみたいでうんざりした。
第三の可能性は、愉快犯、通り魔的犯行。つまり「誰でもよかった」という最低のあれ。でもねえ、女性の通り魔っていうのはあまり前例がないんだよねえと警察は呟いた。だから俺もこの点は考慮しない。
俺に対する個人的怨恨だと、最も疑っていたのは俺の彼女だ。
俺は彼女と同居している。いや、これも正確には「していた」だ。
彼女はおっかけの女の子だった。ライブの打ち上げについてきて、そのあと俺のアパートまでついてきて、あれをしたあと自分の家庭的な不幸を切々と訴えるから「じゃあここで暮らせば?」と軽い気持ちで言ったら翌日の夜、本当に家出してきた。両手いっぱいに荷物さげて。びっくりしたね。それが二年くらい前の出来事だ。
わりとうまくやってたと思う。ただ、彼女には異常に嫉妬深いところがあって、それは彼女の家庭に問題の根本があるのだけれどそれは横に置いとくとして、なにせ自分が「お持ち帰り」された口だから俺の女性関係について疑うのは至極もっともで、いちど疑心暗鬼にかられると理屈も根拠もなく嫉妬がふくらんで爆発するまで止まらない。
そういうわけだからコンビニの事件も、俺に捨てられた女が復讐したのだと信じて疑わなかった。まあたしかに、俺もミュージシャンである以上、潔癖ではいられない。彼女と同居する以前は、何人もの女と別れたし、泣かせてもきた。でも、復讐されるほど酷い仕打ちをした覚えはない。「忘れてるだけよ」って彼女は言うが、元からない記憶は思い出せない。それでも彼女に言わせれば、思い出せないのは俺がそれだけ酷薄だからだ。
ああ、こうして書いてるだけで嫌になってくる。
利き手にぐるぐる包帯を巻いて、箸を持つのも歯磨きするのも難儀している俺にむかって「自業自得」と悪態をつき、ひとかけらの心配りもなかった。
「傷を見せて」としつこくせがむから包帯をほどいて見せてやったら、傷の縫い目がなまなましい俺のてのひらに露骨に眉をしかめて、ひと言、「キモイ」。
キモイだよ。ぶち切れたね、俺は。すさまじい喧嘩になって、それで終わりだ。彼女は荷物をまとめてアパートを出ていった。
怨恨もなにも、君と俺は初対面だった。「初対面」って言い方は変だけど、とにかく初めて出会った。それはたしかだよね。じゃあ君の目的はなんだったんだろう。
誰かに対するっていうより、もっと漠然としたものへの復讐だったのか。それともただ単にむかついていただけなのか。わからない。あのとき、君の顔に「怨恨」とは書いてなかった。「むかつく」とも書いてなかった。じゃあ、なにが君を突き動かしたんだ?
俺の彼女は君に嫉妬していた。返り血を浴びる勇気がなければ復讐なんてできない、相手が誰だろうと。台所でひとり包丁を振り回すのが関の山だ。彼女は君に勝てないと思った。だから出ていったんだ。
そんなわけで、俺はいまひとりだ。バンドを抜けて、女とも別れて、いろんな意味でひとりだ。でも孤独とは違う。孤立でもない。孤高だ。どんなに落ち込もうと、俺は孤高だ。それを君に知ってほしかった。
ねえ君。もういちど聞く。本当に君は俺と面識のない人間なのか。たまたま俺がレジに入ったから俺を傷つけただけで、俺でなくても、誰でもよかったのか。
もちろん俺は君を知らない。だからきっと、君も俺のことを知らない。でもひょっとすると、それは単なる俺の決めつけかもしれない。
警察署で俺はなんども防犯カメラに写った君の画像を見た。見せられた。なんども繰り返し見ているうちに、変な話だけれど、君と馴染みになったような錯覚に陥った。完璧な赤の他人とは思えなくなってしまったんだ。そして無性に君に会いたくなった。変か? 変だな。それは認める。俺は変だ。
君は俺の、それなりに安定した日々を見事にぶち壊してくれた。でもね、あれはみんな、ぶち壊れてよかったものだ。安定をぶち壊すのがロックンロールだからだ。人間、守りに入ったら死んだも同然だ。俺は君を恨んでない。いや、まじで。
ところで俺は、君にお釣りの三百四十円を返していない。それを返すまでは、俺にとっての事件は終わらない。だから返す。返してやる。
抜糸をして、包帯を解いて、傷はふさがった。多少の痛みは残っている。雨の日なんかは特に、傷痕が引きつって、てのひらが痺れる。だけどギターを弾くぶんには問題ない。むしろ痛みが俺をエキサイトさせる。この痛みが俺であり、君なんだ。
中指の付け根から手首にかけて、まっすぐに引かれた白い線。新しい手相みたいだ。本屋で立ち読みして調べたら、運命線といってこれは強運のしるしなんだそうだ。
俺をアホだと思うか。そうだ、アホだ。でも俺はこう思うことにしている。
「俺に起こることは、俺を殺さないことなら、それがなんであろうと俺を強くする」
元ネタはニーチェだ。
俺はいま、アコースティックギターを持って鶴見駅前で歌ってる。夕方の六時から九時まで。バイトがない日は終電まで歌ってる。君は知ってるだろうか。駅前に「コンビニ傷害事件の目撃者を捜しています」と看板が立っている。あの横で歌ってるのが俺だ。
投げ銭入れのギターケースに、いつでも三百四十円は入れておく。見かけたら取ってくれ。それで貸し借りなしだ。
俺たちは再会する。俺は声をかける。君は応える。そこからなにが生まれるのか。わからない。どうなろうと、予測不能な未来に、俺はぞくぞくする。