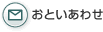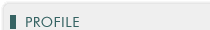志賀泉の「新明解国語辞典小説」
て
ていと
2010/05/16
ていと【帝都】
皇居のある都会。〔明治以後は、東京を指した〕
屋上にのぼると、燕尾服の紳士がいた。
屋上の縁に立って、街を見下ろしている。
自殺志願者ではなさそうだった。ぼんやりたたずんでいる人の後ろ姿だった。
だいいち、飛び降り自殺に燕尾服はいくらなんでも似合わない。あれは晴れの舞台で着るものだろう。もっとも、考えようによっては自殺こそ晴れの舞台だと言えなくもない。
仮にそうだとしても、目の前の紳士は、背中がぜんたいにのほほんとして、追い詰められた感じがまるでない。ぜんぜん切羽詰まっていない。
だから、屋上に燕尾服がいたって別にかまわない。しかし、ひとつ腑に落ちない点は、彼がどうやって屋上にのぼったのかということだ。屋上の出入り口は施錠されていた。ドアの鍵を開けたのは僕だから間違いない。
社員のために開かれた屋上ではなかった。空調機械と電気設備が並び、無数の配管が縦横に延びるだけの屋上は、味も素っ気もない。もっとも、こういう殺風景な場所に癒される人間が世の中には少なからずいるもので、他でもない僕がそうなのだが、僕は窓ふき職人として仕事のためにここへ来たのであって、癒されるためではない。
原則、立入禁止の屋上だ。落下防止の柵も金網もない。膝くらいの高さの出っぱりがあるだけだが、紳士はそのぎりぎりに立って、妙にのほほんとした背中を僕に向けている。
会社のおえらいさんか。それなら屋上のドアくらい「開けゴマ」で開けてしまえる。礼服を着ているのだから式典があるのだ。いや、園遊会かも。早めに準備をすませて時間に余裕がもてた。空いた時間に思索にでもふけろうかと、人目を避けて屋上に出た。東京は本日も晴天なり、と、そんなところか。
いや、そんなことはどうでもよい。僕は迷っていた。どうしようか、困っていた。これから僕は、専門用語で笠木と呼ぶ出っぱりにロープをかけ、窓の外面へと下りていかねばならない。ブランコにすわり、オフィスで働くホワイトカラーをガラス越しに眺めながら窓をふくわけだ。そのためには燕尾服の紳士にどいてもらわないとならない。
なにを悩む必要がある。「どいてください」のひと言ですむ話ではないか。いやいや、そう簡単にはいかない。会社のおえらいさんは、たいがい神経質でわがままときている。ほんの気まぐれで出入りの業者の首を飛ばすくらい朝飯前のすっちょんちょんなのだ。
いや、僕は心配性ではない。経験でものを言っているのだ。三年前まで僕も会社員だった。それが、契約先の社長に「口のきき方が気に入らん」と嫌われ、それがうちの社長の知るところとなり左遷。いろいろあって首が飛び、家のローンが払えなくなり一家離散、浮浪者に転落という不条理な目にあってきた。
さいわい浮浪者生活は三ヵ月で終わり、現在の清掃会社にひろわれた。以来、組織というものにほとほと嫌気がさした。だから、ひとりになれる窓ふき職人を選んだのだが、この国に住んでいる以上、どこでなにをしようと組織は空気みたいについて回る。浮浪者の世界にだって上下関係の縛りはあったのだ。
風はない。絶好の窓ふき日和だ。しかし、空の高いところでびょうびょう風が鳴っている。油断はできない。大気は呼吸する生き物なのだ。
空は冷たく晴れ渡っていた。研ぎ澄ました刃みたいな青空で、朝だというのに星が見えた。夜空の星よりも冴えた光だ。
晴天の星空の下、紳士との距離が詰められないまま馬鹿みたいに突っ立っていた。
気配を察したのか、彼はおもむろに振り向いた。腰をひねるのではなしに、小さく足踏みしながら体を回していく。
後ろ姿の印象を裏切らず、紳士の顔はぬうぼうとしていた。
僕より少し年上。四十代の半ばくらい。丸メガネに小さくすぼんだ目。口髭におちょぼ口。整髪料でぺったりの髪。お茶目なふうで、冷たそうでもあり、気さくなようで、人ぎらいなふうでもあり、とらえどころがない。燕尾服がちっとも似合わず、胸ポケットから突き出たハンカチの端がこっけいなくらい。
紳士はゆらりと揺れた。片手を持ち上げ、肩の高さでひらひら振った。
それから、「やあ」と言った。
どこかで聞いた声。僕はなにかを思い出しそうになった。しかし喉まで出かかった記憶はすぐに、腹の底へ沈んでいった。僕の中のなにが反応したのかもわからなかった。
ただ、不穏な感じはしたのだ。表情は穏やかなくせに、声だけはなぜか暗いのだ。
「あ、どうも」僕は会釈した。「まいど、お世話になってます」
紳士は持ち上げた手で、鷹揚に僕を招いた。
「あの、イゴタ清掃です。窓ふきに来ました」
僕は用心しながら紳士のそばに近寄った。
「窓ふき? ああ、仕事ね。仕事をしたいの」紳士は言った。「高いね、ここは」
「いえ、慣れてますから」
「私は、高いところは苦手だな。馬に乗っただけで足が震えた。ははっ。馬の背というものはね、あれで乗ってみると存外に高い。しかし立場上、乗らないわけにいかなかった。馬上で威厳を保つのはね、君、簡単なようでいて、なかなか大変な仕事だ」
「はあ。乗馬をなさるんで」
「キリンはどうだろう。キリンのほうがよほど高い。君はキリンに乗ったことがあるか。ない。あ、そう。アフリカ人はキリンを手なずけようとは思わなかったのかな。ふむ、キリンの走る姿は見ていて優雅なものだ。しかし乗り心地はよさそうではない」
「あの、仕事してもいいですか」
どいて、と言う代わり、僕は紳士の横を指差した。
「仕事はね、もういいから」彼はこともなげに言った。
「は?」
「窓ふき、したいんでしょ。ここからロープを垂らして」
「あ、はい。それでですね」
「あれはね、いいから」
「いいから?」
「仕事もなにも、君は道具を携えていない。従って仕事にならない」
「へ?」言われて、気づいた。両手に仕事道具がない。足下を見ても、後ろを振り向いても、ないものはない。おかしい。どこに置き忘れたのだっけ。
「そういうわけだから、一服したらよろしい」
紳士はポケットから金色のシガレット・ケースを取り出した。並んだ煙草はフィルターの近くに菊の御紋が入っていた。話には聞いたことがある。恩賜(おんし)の煙草だ。
まじまじと紳士の顔を見た。あ、と息を呑んだ。あの人だ。二十年前に死んだはずの、あの人。いや、年老いて死んだあの人ではない。歴史の教科書に写真があったので覚えている。終戦直後、マッカーサーと並んで立っていた、若い頃のあの人だ。
「吸わないなら私がいただこう。君、すまないが火を」
煙草をくわえ、紳士は僕に顔を突き出した。すぼめたくちびるがまるで無防備だ。僕はポケットをまさぐった。ポケットからネジが出てきた。いったいなんのネジだ。思い出せなかった。
百円ライターは調子が悪かった。火花ばかり勢いよく散って、ついたと思ったら炎は横に倒れ消えてしまう。変だ、風もないのに消える。消える。消える。あ、ついた。
僕は炎を風から守るようにてのひらで囲った。紳士はてのひらの囲いに顔をうずめた。
顔を上げると、紳士は九十前後の老人になっていた。けむりを吐き出す。口と鼻ばかりでなしに、目から耳から頬から額から、顔じゅうから、ふわっと。吸ったけむりが肌を通り抜けているのだ。
「私は死んで久しいから自分では火をあつかえない。しかし君はまだ大丈夫だ」
「あの、気のせいなのかな。いっきに老け込んだみたいな」
しかし本当に驚きなのは、僕があまり驚いていないことだ。
「煙草を吸わないのならキャンディはどうか」
老人はポケットから棒つきキャンディを取り出し、僕に手渡した。チュッパチャプス。こんな味だっけか。眉間が割れそうに甘い。脳髄にずんと響く。
「甘いですね、これ。すごく」
「いまのうちだ。じきに味を感じなくなる。私はもうなにも感じない」
老人はもういっぽんキャンディを取り出し口にふくんだ。それからは、老人は煙草とキャンディを交互に口に運んだ。煙草のけむりはあいかわらず老人の顔ぜんたいから漏れ出ていた。
「味わうということも一種の習慣ではある。生命現象はぜんたい習慣で成り立っているから、習慣が消えればものの味もなくなるのだよ。逆に言えば、死んだ後も習慣が残っている間はものを味わえる。いまのうちしっかり味わうがよい」
「どういう意味ですか?」いやな予感がふくらんだ。
「ヨモツヘグイという言葉は御存知かな」
「いえ」
「そのキャンディがヨモツヘグイなのだよ。ヨモツヘグイをした以上、君もこちら側の人間になったわけだ」
気味が悪くなり、僕はキャンディを捨てた。
「まだわからないか。それは仕方がない。わかりそうにないから私がここに来たのであって、自力で理解できるなら私がここに来る必要はもとからなかった」
「なんだよ。誰なんだよ、あんたは」
老人の顔は四十代の顔に戻っていた。四十代の頬をキャンディがぷくんとふくらませていた。棒の末端をつまむとくちびるがすぼまり、ぽんと音がしてキャンディが抜け出た。くちびるの端が横に広がり、紳士はにっと笑みを浮かべた。
「まだわからない。わからないから私が告げねばならない。死んでいるのだよ、君は」
「うそ?」
「風が強い。こんな日の窓ふきは危ういことこの上ない。しかし君は風に気づかない。なにゆえか」
紳士はキャンディで向かいのビルを示した。向かいの屋上には小さな神社があり、日の丸がはためいていた。なのに、僕は風を感じない。感じられない。紳士の髪にも乱れはない。毛のいっぽんも揺れてはいない。いったい、風はあるのかないのか。
「風が君の体をすりぬけているのだよ」
老人はキャンディの包み紙を指から放した。それは羽が生えたように飛んでいった。
僕は自分のてのひらを見た。てのひらは粉を吹いていた。手を叩くと粉は舞い上がった。ためしに何歩か歩いてみる。足の裏はしっかりとコンクリートの床を踏みしめた。躍起になって足を踏み鳴らす。なんだか頼りない音がした。
紳士はムーンウオークをしていた。
「こんなに元気な幽霊っているかよ」
腹が立ち、かたわらの配管を蹴った。がこんと鈍い音がして、足の甲がしびれた。刃物で刺せばきっと血が出る。ナイフがあれば俺は生きてると証明できるのに。
「いやいや、幽霊の側から見れば生きている人間こそ元気がない」
「幽霊に唾が吐けるか」ぺっと唾を吐いた。「小便だって出せる。出してみようか」
「お好きなように。出したいのなら出るかもしれない。しかし、だからといって君が死んでいる事実に変わりはない。さっきも話したとおり生きているとは習慣のことである。茶碗の持ち方から、細胞ひとつひとつの化学変化にいたるまで生命活動はこれすべて習慣によって維持されておる。いま君が自分を生きていると感じるのも単に習慣がそうさせているだけであって、内実はちっともと伴っていない」
「なにごちゃごちゃ言ってんだよ。いつ俺が死んだんだよ。ちゃんと朝起きて、飯食って家を出て、ちゃんと電車に乗った。それから―」
それから? それからどうしたっけ? それから先の記憶がない。いきなり屋上の記憶に飛んでいる。
「わからないかな。君はさっき、そこのドアを開けもしないですり抜けていったのだよ」
不意の無力感が、僕を襲った。
紳士があらためて差し出した恩賜の煙草に手を伸ばした。諦めの境地で煙草に火をつけた。けむりを吐いたが、悲しみは湧いてこなかった。失業したときや浮浪者に転落したときのほうがよほど悲しかった。悲しみに身悶えして泣き狂ったものだ。
死んで悲しいというのは、僕が死んで悲しむ人がいるから悲しいのであって、悲しむ人がいなければ悲しむ理由もないのだった。いまはただ、ひたすらさびしいだけだ。
向かいのビルの日の丸が風にはためいている。旗の端のほうから布地が少しずつちぎれて風に乗り、飛んでいくように見えたのは、鳥だった。次から次へと日の丸から分かれて飛び立ち、めいめい、輪を描いたり宙返りをしたりしながら、晴天の星空をまちまちな方向へ飛び去っていく。
なにがさびしいのか。失うものがなにもないさびしさだ。この世になにも残せなかったさびしさだ。
「さびしがらなくてよい。たいていの人はたいしたものは残せない」紳士は人の心を見透かすようなことを言った。「残したと胸を張る人に限って、ろくでもないものしか残してないものだ」
「あのさ、人違いだったら悪いけど、あんたむかし、皇居に住んでたことなかったっけ」
「皇居を指して『空虚』と呼んだフランス人がいるが、大変な誤謬(ごびゅう)と言わざるを得ない。皇居ほど豊饒(ほうじょう)な場所が他にあろうか。ない。ないのだ。空虚ほど満ち足りているという東洋思想の逆説を西洋人は理解しない」
「俺、子供んときあんた見たぜ。植樹祭っていうの? すげえ車に乗って目の前を走っていくのを、俺ら沿道に並んで一生けんめい旗ふってたっけ」
「それは、どうも」
「でさ、なんであんた、こんなところにいんの? あんたら、死ねば特別な場所に行くと思ってたけど」
陛下、と呼ぶべきなんだろうと思いながら、「あんた」と呼んだ。
「特別ではないが、みなと同じでもない。むしろいまは、みなよりつらい」
「俺はあんたのこと責めないから。戦争だって、軍人の連中が勝手にはじめちゃったんだろ。学校でそう教わったけど。あんた、神輿に担がれただけなんだよな」
「君は前世から同じ考えだった。当時としてはまことに炯(けい)眼(がん)である。しかし、帝国憲法に定められた統帥権は、そんなに軽々しいものではない」
「俺の前世、見えんの? あんた江原ケイスケかよ」
「戦死した魂は成仏がむずかしいのだ。なにしろ、自分が死んだことにもなかなか気づかないくらいだ。長くこの世をさまよい、生まれ変わっても似たようなことを繰り返す。ほら、現に君がそうだったではないか。運命、と言っていいのかどうか私にはわからない。ただ事実として、そういう場合が多い。彼ら迷える民草に引導を渡すのが私のいまの務めだ。幾万の民草が私の名を呼んで死んだのだ。せめてそれくらいはせねばなるまい」
「引導って、この煙草? さっき、なんとかヘグイとか言った、あれのことか」
「君は、前世のことは忘れただろう。帝都防衛隊として、来たるべき本土決戦にそなえ特殊訓練を受けていたのだよ。いわゆるゲリラ部隊だ。君はビルの壁面をよじ上る訓練の最中に足をすべらせ、ロープが首にからまり宙吊りになって息絶えた」
「あほな死に方だな。聞いてあきれる。笑っちまうくらいだ。それも戦死のうちか」
「そう自虐的にならずともよろしい」
「自虐もなにも、そいつが俺だっていう自覚がぜんぜんないんだけど」
「いや、記憶を失っても痕跡は残るのだよ」
「ああ、デジャブってやつ。俺、あったよ。子供の頃なんか、しょっちゅうだった。不思議だよな、あれって」
「いや、デジャブではない。それは単なる思い込みでしかない」
「あっそ。別にいいけど」
恩賜の煙草は、いくら吸っても短くならなかった。煙草を持つ指の皮膚からけむりが漏れ出ているのに気づき、怖くなって煙草を捨てた。足で踏みにじろうとしても踏みにじれない。煙草を踏んだ足の甲を通り越して、けむりは立ち上っていた。
「時間というものを川の流れによくたとえるが、あれは間違いだ。時間は流れるのではなく降り積もると考えたほうが正しい。降り積もった時間はやがて地層を成す。おわかりかな? 新しい地層をめくればその下から古い地層が現れる。その地層をめくればもっと古い地層が現れる。幾層にも重なった地層の上にいまこの現在がある。さ、ここへ。遠慮せずに、私の隣へ。ごらんのとおり。時間の層をめくれば、現在の下に焦土と化した東京が現れる。さあ、思い出せるかな。君は前世でこの風景を見ていたはずだが」
「すげえな」
東京がいちめん焼け野原だ。ところどころ、瓦礫やトタンの隙間から、煮炊きのけむりが細く上がっている。けむりはまっすぐに立ち上り、空に吸われて消えていく高さを、さっき日の丸からちぎれて飛んでいった鳥が舞っていた。
「『東京物語』という映画があるのを御存知かな。御存知でない。まあよい。私はあの映画を何度も見た。よい映画だった。地方から出てきた老夫婦が高みから東京を見下ろす場面があるが、カメラは老夫婦の背中ばかり写して二人が見下ろしている東京の街をいっこうに映さない。二人が実際、なにを見ていたのかわからない。それがあの映画の勘どころだと思うが、どうか」
「あのさ、俺みたいなやつがこの世に腐るほどいるんだろ? そうだよな? そのひとりひとりと、こんなふうに付き合ってんの? あんた死んだよって教えて回ってんの。体がいくつあっても足りねえだろ」
「我が身がひとつとは限らない」
紳士は、向かいのビルを指差した。いつの間にか、元のままの東京だ。
向かいのビルは屋上に小さな神社がある。ほこらの扉がひとりでに開き、黒い革靴の足が突き出たかと思うと、タコが蛸壺から出てくる具合にぬるっと全身が現れた。軟体動物のようなぐにゃぐにゃの体がしゃんとすると、こちら側の紳士とうりふたつだ。そいつは赤い鳥居をくぐり、「やあ」と言うようにこちらへ片手を上げた。
こちらの紳士も、「やあ」と片手を上げた。それが合図だったように、向こう側の紳士の体がばらばらになり、無数の黒い鳥となって空へ散っていった。
「追って沙汰があろう。それまで、これでも舐めて待つがよろしい」
紳士はあらためて僕にキャンディを手渡した。キャンディはさっきほどは甘くなかった。甘いことは甘いが、脳髄にずんと響くような甘さではなかった。
紳士は、また老人の顔になっていた。
口髭が片方、斜めにずれている。あれ、つけ髭? と思っている間に、丸メガネのレンズが青白く光りだし、細胞がスパークしたみたいに体のあちこちが放電し、点滅を始めたかと思うと、ぷつんと消えた。ちりちりと電気のはぜる音が残った。
僕は屋上にひとり取り残され、あほうのようにキャンディを舐めながら、地上を見下ろした。眼下に広がっていたのは焼け野原の東京だった。ビルやら車やらでごちゃごちゃした東京よりも、むしろさっぱりとして気味がいいくらいだ。
これから沙汰があるらしいが、僕はどうなるのだろう。また生まれ直すなんて、考えるだけで疲れる。逃げちまおうかと、思いきって屋上の縁を蹴り、空に躍り出た。
落ちると思ったが、僕は空を飛んでいた。上空から見下ろすと、いちめん灰色の焦土の中にあって、皇居の森は島みたいだった。
くわえていたキャンディをうっかり落とした。皇居前の広場で泣き伏している兵士の頭に、それは命中した。
「あいたっ!」と声がした。