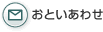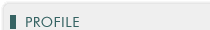志賀泉の「新明解国語辞典小説」
つ
つりかわ
2010/05/03
つりかわ【吊革】
〔電車・バスなどで〕立ってる客がからだをささえるためにつかまる、輪のついた(革製の)ひも。
―?
滝田伸之(45歳独身 離婚歴あり)は目を疑った。
滝田の頭上に疑問符の「?」が躍り上がった。「?」はやがて逆立ちして、肉屋の吊るし鈎みたいに、滝田が信じていた現実を宙吊りにした。
何だこれは?
土曜日の朝だった。昨夜はぐでんぐでんに酔い潰れ、正体をなくしたまま帰巣本能で電車を乗り継ぎ家に帰った。記憶はまったくないが、こうしてベッドで目覚めたのだから、そうなのだろう。
着のみ着で寝ていた。スーツを着たまま、靴下も履いたまま。ネクタイだけは無意識に外したらしく枕元でねじれている。アルマーニのネクタイがまるで蛇の抜け殻だ。
よかった。目覚めれば警察署のブタ箱、なんてことにならなくて。記憶をなくしている間の自分にまで責任を持てるものか。夢の中の行為で処罰されるようなものだ。痴漢しようが暴力を振るおうが、身に覚えがなければ反省のしようもない。
イタリア製のブランド・スーツがひと晩でよれよれだ。スーツを脱ぎ、ズボンを脱ぎ、靴下も脱ぎ、無造作に丸めて下着姿になると、深酒した翌朝特有のべとべとした寝汗が肌から匂い立った。胸がむかつく。自分にがっかりする。年齢を感じるのはこういう時だ。飲食店の裏口で生ゴミ用のポリバケツが立てるような匂い。汗が腐っているのだ。
まったく、新入社員の歓迎会なんてろくなもんじゃない。最初は「取りあえずビール」なんだよ。酎ハイやカクテルで乾杯ができるかっての。大学のサークルじゃないんだ。
新年度が始まったからといって、新しいことなど何ひとつ始まらない。新しい、という錯覚だけが独り歩きして、会社の体質は旧態依然のまま、どんどん時代に取り残されていく。新入社員もそれを承知で入社しているのだ。
バブル最盛期に入社した滝田にとって、昨日の歓迎会は惨めたらしい空騒ぎだった。二次会を断り、一人で飲み直した挙げ句がこのざまだ。
二日酔いの頭には小人が住んでいる。金鎚を手に内側から頭骨をゴンゴン鳴らす。カーテンが開け放しの窓から朝の光が差し込み、よどんだ脳をしらじら照らし出す。
取りあえず煙草を。まったく、昨夜は喫煙者と非喫煙者の席を分けたおかげで、滝田はおじさん席に押し込められた。近頃の若者は煙草を吸わない。あえて健康に背を向けるダンディズムをまったく理解しない。ぶつぶつぼやきながらスーツのポケットを探ったが煙草がない。鞄に入れたのかと、質流れのブランド品を扱う店で買った書類鞄のチャックを開けたら、なんと吊革が出てきた。
―吊革?
目を疑った。
電車やバスの天井近くから吊り下がっている、あれだ。プラスチックの白いリングと、灰色をしたナイロンのストラップ。その先が輪っかになっていて。留め具を保護するプラスチックの平たい筒。そこに小さな広告スペースが空いていて。
何の変哲もない。ありふれた吊革だ。しかし、そのありふれた物が、あり得ないところから現れると、きっかいな、見慣れない物に変わった。
何だこれは?
最初、酔った勢いで持ち帰ったのかと舌打ちした。しかし次の瞬間には、ありえない、と考え直した。そんなはずはない。輪っかがしっかり閉じているのに、どうすれば鉄パイプから外れるのだ。
鞄の口から滑り落ちて床板に転がった吊革が、ひどくグロテスクに見えた。まるで未知の生物の骨。こめかみがうずき、親指と中指で揉みしだいた。二日酔いとは別の、妙な胸苦しさが襲った。
滝田はベッドに腰かけたまま足を伸ばし、怖い物を払い除けるように吊革をつま先で蹴った。吊革はほんの少し床板を滑っただけだった。足の先から戦慄が這い上がり、すね毛がざわついた。吊革は生きているように見えた。リングが首をもたげ、床板を這うような動きをしたのだ。いや、錯覚だ。息を詰めて吊革を凝視したが、吊革はぴくりとも動かなかった。
煙草は鞄のポケットに入っていた。煙草をくわえ、舶来品のライターで火をつけ、煙を吐く。壁に、ムンクの「叫び」。気を落ち着けてから「なぜ?」と考えた。しかし思考は足踏みし、頭痛ばかり激しさを増す。思考は「なぜ?」の外へ一歩も踏み出せなかった。煙草の煙はちっとも空中に広がらず、滝田の周囲にまとわりついた。意識の混乱が吐き気を誘い、内臓まで重苦しくなった。
吊革は吊革そのものだ。つまり、電車の天井近くの鉄パイプにくるんと巻きついていた輪っかが、輪っかのままで切れ目はなく、留め具を外した形跡もない。だいいち、留め具はプラスチックの平たい筒に隠れているのだ。
俺はいったい何をしたのか。どんな手品を使ったのか。記憶にない。首を振ったって何も出てきやしない。鞄の中に女の手首が入っていたとか、ぶ厚い札束が入っていたとかなら、驚愕こそすれ、理解の範囲ではある。どんなに謎めいていても「現実」なのだ。吊革は、それ自体は平凡なくせに「現実」を超えている。
どう考えても、吊革はそのままの形で外れたのだ。握っていた吊革が何かの拍子で鉄パイプからずるっと抜け落ち、事態をよく理解しないまま、慌てて鞄に隠した。そして忘れた。あり得ないことだが、そう考えるよりほかにないではないか。
滝田は手のひらを広げてじっと見つめた。手のひらが汗をかいていた。
吊革は、滝田の日常に忍び込んできた異物だった。その異物が、さりげなさを装って床に転がっている。滝田の足下で、ありふれた朝陽を浴びている。
とにかくも裸になり、浴室に入る。熱いシャワーを浴び、体が火照ってくると、耳の奥でピシッとピンが外れるような音がした。そして「超能力」という言葉が脳裏に浮上した。
超能力で鉄パイプから吊革を外した?
荒唐無稽だ。ばかばかしい。でも、それ以外にどう説明する? 落ち着け。超能力を認めてしまえば、それがいちばん理にかなった考え方なのだ。
俺には超能力があった。酔っぱらって、無意識に潜在能力を発揮したのだ。
そうか、俺は超能力者だったんだ。
滝田はシャワーの勢いを強くした。なんとも言えない高揚感が腹の底から湧き上がり、濡れた頭を掻きむしった。
「超能力者」という自覚は、「選ばれし者」という優越感に直結した。
滝田が小学生の時、超能力ブームが日本を席捲した。
ある日、テレビで超能力を検証する番組があり、アメリカ人の超能力者が生出演しテレビ中継を使って全国の視聴者に念を送る実験をした。念を受け取った者は潜在能力を発揮し手にしたスプーンが曲がるかもしれない。滝田は台所に走り、スプーンを握ってテレビの前に戻ると懸命にスプーンをこすった。父と母は笑った。テレビの向こうではスタジオに並んだ電話がつぎつぎ鳴り響き、全国から「曲がった」という報告が寄せられた。「やらせ」という言葉すらなかった時代だ。スタジオは沸き返り、「実験は成功です」と叫ぶ司会者の声が上ずった。
滝田のスプーンは一ミリだって曲がらなかった。しかし諦めきれず、番組が終わってもこすり続けた。こすりながら、挫折感を深めていった。ついにスプーンを投げ出した時、滝田は見捨てられたと感じた。
翌日、学校に行くと、クラスはスプーンが曲がった子と曲がらなかった子とに分かれていた。「曲がった」と言い張る子の多くは、日頃から我の強い、目立ちたがり屋だった。「覚醒した」と彼らは言った。優越感に浸り、「選ばれし者」を自称した。スプーンを曲げただけで「ニュータイプ」だった。滝田は彼らの嘘にうすうす気づきながら、それを言い出せば「嫉妬」を認めてしまうことになると知ってもいた。
超能力とは「自分は特別だ」と思いたがる人の妄想であり、嘘なのだ。幼い頭で滝田はそう解釈した。
滝田はバスタオルを腰に巻きつけ、寝室に戻った。
あらためて吊革を見下ろせば、それは謎めいた物でも、驚異をもたらす物でもなくなっていた。滝田はベッドに腰かけ、吊革を手に取ると、曲げたり引っ張ったりし、回転をつけて空中に放り投げてはつかまえる、という動作を繰り返した。
朝食をとり、テレビを見ているうちに眠りこけ、目覚めてみれば二日酔いは消えていた。吊革は消えていなかった。消えていたのは興奮だった。眼差しが妙に醒めていた。
俺は「選ばれし者」になりたかった。「自分は特別だ」と思いたかったのだ。しかし、これが超能力の結果だとして、だからどうなのだろう。酔った勢いで窃盗を働いたのと、どう違うのだろう。
多くの人間に握られ薄汚れた吊革の凡庸さは、そのまま滝田の凡庸さを示していた。
バブル最盛期の年、飛ぶ鳥を落とす勢いだった有名百貨店に滝田は入社した。自分を「時代に選ばれた者」だと思い込んだ。その百貨店は単なる流通業を超え、文化の担い手として脚光を浴びていた。株主である大物歌手を招いたショーさながらの入社式はテレビニュースになったくらいだ。ウイットに富んだポスターは時代の象徴として新作が出るたび話題を呼んだ。会社は個性の発揮を奨励し、滝田は真に受けた。しかしそれは、時代が押しつけた個性だった。滝田の自意識は会社の膨張と一体化して拡大していった。
事実は事業拡大のための大量採用の一人に過ぎなかったが、滝田は「選ばれし者」の高揚感に浸りながら死ぬほど働いたものだ。
しかし、時代が人を選ぶのではない。人が人を選ぶのだ。
今、滝田は系列のスーパーマーケットの企画室長だ。企画室といえば聞こえはいいが、要するに閑職だ。
最近の若い者には上昇志向がない。ほどほどで満足してしまう。滝田にはそれが理解できない。人並みになるには人一倍の努力が必要なのに、人並みの努力で良しとするからいつまでも人並みになれない。すぐに自信を喪失する。傷つく。上の世代を煙たがり、内輪でかたまる。
生活費を削りながらブランド品に固執する自分を彼らが嘲笑していることを滝田は知っていた。いずれ疎んじられていくのは目に見えているのに、なぜそんなやつらをおだてるために歓迎会を開かなければならないのだ。
いっときの興奮が醒めてしまえば、薄汚れた吊革はひどくみすぼらしい物に見えた。
もしも本当に超能力で吊革を鉄パイプから外したのだとしても、それが何になるというのか。素晴らしい能力だと誰に向かって誇れるのだ。つまりは自分の無力さを証明して終わりではないか。超能力ブームの時代に、あまた登場し消えていったスプーン曲げ少年のように。
滝田は吊革をステンレスのものほしざおに通し、ベランダに吊した。凡庸な吊革にはそれがふさわしい在り方に思えた。
吊革のリングを通して見る空は小さい。この小さな空が、自分につかめるサイズなのだ。
間抜けだ。滝田は笑った。吊革は自分の似姿だった。
夕暮れになり、滝田はベランダに出て吊革につかまった。夕陽は、目の前にそびえる高層マンションの後ろに落ちていく。後光を背負い、陰影を帯びていく高層マンションに、ぽつりぽつり明かりが灯っていく。夕暮れ時は街の音がよく通る。スーパーマーケットが流すBGMや、遠い駅の発車チャイムの音までがくっきりとした輪郭をもって聞こえてくる。
吊革につかまっても、電車のように風景は流れていかない。どうしようもない停滞感だけがある。
停滞感が、悲哀になって唐突に滝田を締めつけた。吊り革につかまって、どこに行けるのか。根拠のない目標ばかり掲げて、どこにも行き着けない。果たせないとわかっている約束なら最初からしなければいいのに。だから妻も出ていったのだ。
どこにも行けないなら、せめて体くらいは揺らそう。転ばぬために、自分を支える物があるなら、それがどんなにつまらない物だろうと、今はしっかり、握りしめているしかない。
暮れていく街を見下ろしながら、滝田はいつまでも揺れていた。