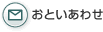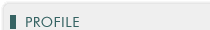志賀泉の「新明解国語辞典小説」
ち
ちゅうがえり
2010/04/12
ちゅうがえり【宙返(り)】
①とんぼがえり。②飛行機が空中でする垂直方向の回転。
やれるかな、と浩雄は考えた。やれるかもしれねえな。
正体不明の力が、腹の底にみなぎりつつある。
なにかの力が、体を突き動かそうとしている。
たぶん、やれるな。一度そう考えると、「たぶん」は「きっと」に変わった。
きっとやれる。
走り出す前から、ある種の浮遊感が全身に湧き起こってきた。
放課後。ガッコウの裏庭。浩雄は壁の前にいた。
図書館とプレハブ倉庫に挟まれた、幅十メートル高さ五メートルの黒ずんだコンクリート壁。そのすぐ向こうに隣家のタイル張りの壁がある。
習慣って、怖い。無意識ってやつは背後霊みたいだ。玄関を出て校門へ向かうのに、遠回りになる裏庭をいつの間にか歩いてた。気がつけば壁の前だ。我に返って、自分に呆れた。ぼんやりにもほどがある。なんで俺、ここにいるんだか。
図書館に行くのでなければ誰も裏庭なんて通らない。浩雄にしても、テニスの壁打ちを禁止されてから裏庭に用はなくなったはずだ。壁打ちの音がうるさいと隣家の婆さんが苦情を入れたからだ。
放課後のたった一時間だぜ。青少年の育成より婆さんの余生が大事か?
死ねよ、ばばぁ。
おかげで壁の前の空き地は来客用の駐車場になった。たった三台分の駐車場。コンクリートの地面にペンキで白線を引いて。その白線が微妙にゆがんでいて。いま、そこに車は一台もない。壁は浩雄に向かって開放されていた。
テニス部を抜けてから四ヵ月、毎日この壁と付き合ってきた。壁打ちの他にすることがなかったし、することがないといらいらした。力いっぱい壁にボールを打ち込んで憂さを晴らしていたのに。その壁さえ奪われて、浩雄は心から腐っていた。
黴と埃で黒ずんだコンクリートの壁面に、ボールの跡が白抜けして無数に残っている。どれもこれも浩雄のいらだちの痕跡だ。それは中央に集まり、目の粗いドットみたいで、人の影にも見える。俺の影みてえだ、と浩雄は思った。
その影が今、浩雄を挑発していた。飛べ。
失敗したら大ケガするよな。
成功したって誰も誉めないし。
でも、このまま素通りするのは自分から逃げるみたいで嫌だ。
浩雄は鞄を地面に置き、辺りを見回してから壁に向き直った。
壁に呼ばれてここに来たのなら、やっぱ飛ぶしかねえか。
挑発してんのなら乗ってやるよ。俺の影を俺の足で踏んづけてやる。
なにしてんだろ?
やっぱりそうだ。あの子、毎日あそこで壁打ちをしてた子だ。
恵子は図書館にいて、窓際の席から浩雄を見ていた。
恵子の家は親が一階でスナックを営業している。できれば普通のサラリーマン家庭に生まれたかった。夜はカラオケの声が二階まで響いてうるさいから、勉強はいつも図書館でする。親が国立以外の大学は経済的にムリって言う。大学に行きたいから人並みに勉強はする。友達にはマジメと思われ敬遠されがちだが、家ではほとんど勉強をしない。オヤジ達の自己陶酔の歌声が床の下にとどろく部屋で、弟とゲームとかして遊んでいる。
毎日図書館で勉強をしているから、壁打ちの音は自然と耳に入った。窓際の席に座ればテニス少年の姿も見えた。彼はたぶん一年生で、王子様とまではいかないまでも、まあまあいけてる。クールで、ワイルドで、しなやかで。ただの趣味にしては異常に熱心で、壁を相手に攻撃的だった。あんなに好きならどうしてテニス部に入らないのか不思議だった。
隣家のお婆さんの苦情で壁打ちが禁止されてから、彼はぷっつり姿を消した。壁打ちの音を楽しんでいたわけではないが、いつも聞いていた音が聞こえなくなると、なんだか物足りない。なにしろ激しい音だった。殺気立ってもいた。ボールの音が自分のなにかを刺激していたんだと、音が消えてから恵子は気づいた。
そのテニス少年が、数日ぶりで現れたと思ったら、手ぶらで壁と向き合っていた。なにしてんのかなと思って見ていたら、彼は壁に向かっていきなり走り出したのだ。
あ、ぶつかる! 恵子は目をつぶった。数秒後に目を開けてみたら、彼は壁の手前で倒れていた。
なに? なにがあったの?
わけがわからなかった。とにかく恵子は勉強を中断し、ノートと参考書を鞄の中に放り込んで図書館の外に出た。心配して、というより、彼と会って話をしたかった。実を言えば、彼から壁打ちの場を奪った本当の原因は、自分にあるかもしれないからだ。
浩雄は壁の前に倒れたまま、苦しそうに反り返っていた。
「大丈夫? 誰か呼ぼうか」
恵子は、おそるおそる近づき、声をかけた。
「いってえ」浩雄は顔をゆがめ、きつく歯を食いしばってツバを飛ばした。「背骨折った。救急車呼んで」
恵子は真に受け、慌てて携帯電話を開いた。
「嘘だよ」ひと言吐き捨て、浩雄はつらそうに上体を起こした。「ほんとに背骨折ったら声なんか出ねえ」
人が心配してるのに、なによこの態度。恵子はむっとしたが、口から出た言葉は彼を気づかっていた。
「じゃあ保健室行く?」
「あそこ、バンドエイドと正露丸しか置いてねえんだ」
わざとらしい顰(しか)めっ面で背中をひねり、苦笑いを浮かべる。
ああ、照れ隠しなんだ。男の子ってかわいい。恵子はほっとした。
「宙返りしようとして、失敗した」浩雄は両足を前に投げ出し、後ろ手をついて背筋を伸ばした。
「宙返り?」下着が見えないようスカートを押さえて、恵子はしゃがんだ。
「サマーソルトキック。プロレス技、知ってる?」
「なんか、名前は聞いたことある」
「コーナーにいる敵に蹴りを入れながらバック宙する技。知るわけねえか」
「あ、それ、足からソニック・ブームが出るんだっけ?」
「ソニック・ブーム? なんだそりゃ」
恵子が思い出したのは格闘ゲームの技だ。恵子は格闘ゲームを好まないが、弟が好きなのでたまに付き合う。たしか、バック宙しながら相手に蹴りを入れる技だ。
浩雄はゲームをしない。だからソニック・ブームなんて知らない。壁の手前でジャンプし、その勢いで一歩、二歩と壁を駆け上がり、壁を蹴って背中を反らして後方回転、着地を決める。うまくいけばそうなるはずだった。
浩雄が説明すると、
「できんの?」と恵子は目を丸くした。
「できると思ったんだよ」
「思っただけでやっちゃうんだ」
「仕方ないだろ、できると思ったんだから」
イメージはできていた。跳躍力もある、体も柔軟だ。なのに、地面を蹴ってジャンプする直前に、一瞬の迷いが生じた。その時、浩雄の脳裏をかすめたのは、どこかの航空ショーで宙返りに失敗した飛行機が地面に激突し炎上するテレビの特番の衝撃映像だった。
結果、ジャンプはしたものの壁を蹴った反動で後ろにすっ飛び、背中から転倒した。痛いのなんのって、衝撃で肺が破裂したかと思った。しばらく呼吸が止まったくらいだ。
「なんで? なんでそんな真似するの?」
「理由がないとしちゃ駄目か」
「頭打ってない?」
「打ったら死んでた」
浩雄は恵子をうるさく感じた。たぶん二年生だ。どうして俺にかまうのだろう。
平気だということを証明しようと立ち上がったが、背中が痛くてうまく歩けない。
「ほらね」恵子は言った。「そこのベンチで少し休もう」
先週のことだ。恵子は自転車を飛ばしていて、隣の家のお婆さんとぶつかった。いや、ぶつかりそうになったのだ。
お婆さんは独り暮らしだ。達者なお婆さんで、毎朝歩道に出て街路樹の落ち葉を竹ボウキで掃いている。自分の家の前だけでなく界隈の歩道を勝手に引き受けて掃除している。竹ボウキがよく似合うので「レレレのおばさん」と呼ぶ生徒もいる。
その日、いつもは徒歩通学の恵子が自転車を走らせていた。遅刻しそうになって、というか、とっくに一時間目が始まっている時間だ。昨夜遅く、スナックのお客さんが酔って暴れて救急車やパトカーまで出動する騒ぎになり、眠れなかった。家族そろって寝過ごしたのだ。必死でペダルを漕ぎながら「コロス」と口走っていた。誰を殺したいのか。なんだかんだいって親は大切。弟はかわいい。自分はもっとかわいい。強いて言えば昨夜の客だが、どういう人か見てないので殺意は湧きにくい。だから「コロス」と口にしても大した意味はなく、本当に人を殺したいわけじゃない。
焦っていて、街路樹の影にいたお婆さんが見えなかった。お婆さんが竹ボウキを手にぬっと現れ、びっくりしてハンドルを切ったが遅かった。恵子の目から火花が散った。
ぶつかった? いや、ぶつかったのはホウキだけ。ホウキの柄が恵子の額に当たってかなり痛かった。ふらつきながら急ブレーキをかけた。ふり返り、「ごめんなさい」と謝ろうとして、言葉が声にならず口パクになった。
お婆さんが歩道の端で尻餅をついていた。なんで?
わけがわからなかった。当たったのはホウキだけなのに、なんでお婆さんまで転んでるわけ? 慌てて引き返そうとして、体が固まった。怖くなった。相手は年寄りだ。ちょっと転んだだけですぐ骨を折る。寝たきりになったらどうしよう。損害賠償を何百万も請求されたら親に迷惑をかける。大学どころか人生破滅だ。
そんなこんなが高速で脳裏を駆けめぐり、恵子は逃げた。幸いにして目撃者はいない。轢き逃げだ。立派な犯罪だ。老人の残り少ない寿命より私の未来が大事だ。
先生には、お腹が痛くなってと嘘をついた。恵子の青い顔を見て先生は疑わなかった。しかし、その日一日、恵子は生きた心地がしなかった。お婆さん、大丈夫だろうか。いまさら謝りに行ったって遅い。自殺行為だ。じっとしてよう。でも警察が来たらどうしよう。お婆さんが車椅子で教室に現れ、正面から恵子を指差す場面を想像してぞっとした。
胸を押し潰しそうな不安とは裏腹に、不思議なくらい恵子の身辺は平穏だった。そういえば救急車のサイレンの音も聞こえてこない。
翌朝、普段どおり竹ボウキを持ったお婆さんを見て、恵子はほっと胸を撫で下ろした。頑丈なお婆さんでよかった。無傷ですんだから、昨日の事故を警察に届けず、ガッコウにも黙っていてくれたのだ。
そうよね、事故はお互いさま。私だってホウキが顔に当たって痛かったんだから。
あの時、声にならなかった「ごめんなさい」は、結局、宙に浮いたまま放置された。
しかし、翌週の月曜日のことだ。朝礼の最後に、教頭先生がこう言ったのだ。
「裏庭の壁を使って一部の生徒がテニスの壁打ちをしておるようですが、その件で隣の家からうるさいと苦情が入っております。そもそもあの場所は運動場ではありません|」 なんで? 恵子の目がテンになった。お婆さんの嫌がらせ? 自転車事故で腹を立てたお婆さんが、事故とはなんの関係もない壁打ちに怒りの矛先を向けた。そうとしか思えない。でなければ、ずっと前から続いていた壁打ちに、なぜこのタイミングで苦情を言ったのか説明がつかない。
私がお婆さんを転ばして逃げたばっかりに、最近の若者は怖いっていう紋切り型のイメージがお婆さんの頭に焼きついて、今までは平気だった壁打ちの音まで凶暴に聞こえ始めたのだ。家の中に響くボールの音に脅かされて、耐えられなくなったのだ。
テニス少年にとっては、いいとばっちりだ。
あの事故は表沙汰にはならずにすんだが、罪悪感は消えなかった。
壁の前で倒れていたテニス少年を見て駆け寄ったのも、お婆さんを見捨てて逃げた罪悪感を、少しでも軽くしたい気持ちからだった。
気持ちのすり替え、と言われればそれまでだけど。
恵子は購買部に置いてある自販機で缶入りのポカリスエットを買い、浩雄におごった。
浩雄は、見ず知らずの上級生に親切にされる理由がわからず、ポカリスエットを飲んでいいのか迷い、しばらくは両手の中で転がしていた。
「飲まないの?」恵子にうながされ、「人におごってもらうのは苦手なんだ」と、浩雄は首をかしげた。それでも、ポカリスエットは放さなかった。
「二年生?」と訊かれて、恵子はうなずいた。
「じゃあ俺のいっこ上だ。年上におごってもらうと、なんかさ、その人に従わなくちゃならなくなる気がして」
「めんどくさい人だね」
「俺がめんどくさい以上に、世の中のほうがめんどくさい」
浩雄がテニス部を抜けたのも、先輩のおごりがきっかけだった。
夏休み。他校との交流戦がぼろ負けに終わった帰り道でのことだ。
駅の近くの公園で反省会を開くことになり、先輩の一人が「ヒロオ。ちょっとコンビニまで走って人数ぶん飲み物買ってこい」と命じた。浩雄は、先輩が差し出したお金を受け取らなかった。
「俺、いいです。自分のペットボトルありますから」
自分は要らないのだから、買ってくる義務はない。つまりそう言ったのだ。
「あっそう。じゃあ自分のは抜かしてみんなのぶん買ってこい」
先輩は、あくまで浩雄に使い走りをさせるつもりだった。浩雄は拒み、それでも先輩がお金を引っ込めようとしないので、お金を受け取りくしゃくしゃに丸めて地面に捨てた。千円札が二枚だった。それで喧嘩になり、浩雄はテニス部を抜けたのだ。
「子供の喧嘩だ」恵子は口に出した。正直、がっかりした。「つまんない理由」
「その先輩より俺のほうが強いんだよ。なのに先輩がレギュラーで俺は補欠なんだから、ぜったい変だろ。先輩も内心じゃそれ認めてて、だから俺に使いっ走りさせてたんだ。そうでもしなきゃ自分の立場ないから、むりやり先輩風吹かせて」
「でも、どうせ先輩はいずれ辞めてくんだし。しばらく我慢すれば自分がレギュラーになれるんだし」
「なんで年功序列なんだよ。だから部活って嫌いなんだよ」
「おかしいと思ったら、自分が先輩になって変えればいいじゃない」
「正論ばっか吐く女って嫌だ。上から目線で、学級委員長みてえ」
「耳に痛いんだ」恵子は笑った。笑いながら「それ、飲めば?」と再びうながした。「私は、自分が飲みたくてついでに買ってきただけだから」
言いながら、自分の缶コーヒーを飲んだ。それを見て、やっと浩雄もポカリスエットの口金を開けた。
あ、ピアス。恵子は心の中で声をあげた。浩雄の耳にピアスの穴があった。ピアスはしてなくて、やわらかそうですべすべの耳たぶに、小さな穴がぽつんと。その穴に、彼の子供みたいなプライドが凝縮されてるみたいで、恵子はその穴を愛おしく思った。
「それでかあ。趣味で壁打ちしてるにしては異常に一生懸命だったもんね。実はやけくそだったんだ」
「うん、まあ。テニス部のコートまで音が届けって思ってたから」
「じゃあテニス部に未練があるんだ。隣のお婆さんにはいい迷惑だったろうけど」
「どうしようかな、俺」浩雄は両足を前に投げ出し、空を見上げた。「壁打ちにちょうどいい壁だったんだよなあ。放課後に暇だと犯罪でもやらかしそうで。俺が犯罪者になったら責任とれよな、隣のくそばばぁ」
自転車事故のことを打ち明けようか、恵子は迷ったが、やっぱり言い出せなかった。肝心なことを隠して諭すようなことを口にしている自分が卑怯者に思えた。
「隣の家とガッコウの壁との隙間、このくらいしかないんだから」
恵子は両手で、二十センチくらいの幅を作った。「きっと、すごい響くよ。銃弾みたいに。ボールの音がするたび寿命が縮んだかも」
「一日に一時間ちょっとだぜ。その間だけ耳ふさいでくれたっていいじゃん」
「仕方ないよ。相手は年寄りだし、独り暮らしなんだし。ただでさえ心細いのに、あの音が家の中にビンビン響いて、怖かったんだよ」
怖くなったのは私のせいだと、やっぱり打ち明けられなかった。
「テニス部に戻るしかないかなあ」浩雄はふと、漏らした。「でも、いまさらなあ」
「謝ればいいのに、ごめんって」
「そのひと言が難しいんだよ」
「簡単だよ、ごめんって言うくらい。少なくとも宙返りするよりは簡単でしょ」
「やっぱ俺が変わるしかないかあ」浩雄は溜め息をついた。
空を見上げた。青空にひこうき雲が白い直線を引いていった。
「さかあがりってあるだろ」浩雄は続けた。恵子がうなずくのを見て話し続けた。「小学校の時、みんな一生懸命さかあがりの練習したろ。なんか、これできなきゃ人間失格みたいに必死こいてさ。そんで、初めてさかあがりに成功したとき、やったあって喜んだろ。なんであんなに嬉しかったんだろうな。鉄棒の上に乗っかっると、校庭がやたら広く見えてさ。ぐるっと一回転しただけで、こんなに世の中が変わって見えるんだってびっくりしたの覚えてる。あれ、世の中が変わったんじゃなくて自分が変わったんだよな」
浩雄は話しながら、壁を前にした時に自分を襲った高揚感はこれだったんだと思い出した。要するに俺は変わりたかったんだ。
背中の痛みが引いて、浩雄は立ち上がった。
「なんか俺、今度はやれそうな気がする」
そうして再び壁に向かった。
何度かシミュレーションして踏みきりの位置を決め、壁を蹴る足の高さも見当つけた。準備は万全だ。後は勇気の問題だ。
成功と失敗を分けるのはつまり、ためらいを後ろ足で蹴る思い切りの強さだ。
恵子は横で見ていた。思い切りのいいジャンプだった。
浩雄は高く跳び、壁を蹴った足はつま先で空中に大きな円を描いた。浩雄はくるんと回った。勢いがありすぎて着地の後に尻餅をついたものの、背中を丸めて危なげなく転がった。「いってえ」とまた叫んだが、まあ、成功と言っていい。
二人は並んで校門を出た。
お婆さんの家はひっそりとして、古風な格子戸の門のわきから、柵を越えて庭木が枝を張り出し、イヨカンだかハッサクだか、柑橘系の大きな果実がたわわに実っている。
「食えんのかな、あれ。あんなにまっきっきでほったらかしにして」浩雄は言った。
「なんか酸っぱそう」
恵子の頭に、ひとつのアイデアが不意にひらめいた。
鞄から黒のサインペンを取り出し、手を伸ばして果実のひとつを引き寄せると、黄色い果皮に字を書いた。
「落書き?」
浩雄は首を伸ばして恵子の手元を見た。果実には「ごめんね」と書いてあった。
「なに謝ってんだよ」
「だから、君の代わりに謝ってあげてんの」
「よけいなお世話だよ。これでいいんなら俺だって出来るし」
浩雄は恵子の手からサインペンを奪った。
「じゃあ君は、私の代わりに謝っておいて」
「なんで? お婆さんになんかした?」
「ちょっとね」
浩雄はそれ以上追及せず、三、四個、高い所にある果実に手を伸ばし「ゴメン」と書いた。ゴメン、ゴメン、ゴメン。メールの顔文字っぽく反省顔のイラストも描き添えた。
これでは釣り合いがとれなくなるので、恵子は浩雄からサインペンを返してもらい「ごめんね」を二、三個書き足した。
「これ見たら逆に怒りだすんじゃねえかな」
「怒るかもしれないけど、きっと寿命は延びるよ」恵子は言った。
それから、少し離れて落書きのある果実を見上げた。
「すげえ。現代アートじゃん」浩雄は言った。実際、壮観だ。
またガッコウに苦情が来るかもしれないな。でも、そうなったら謝りに行こう。今度こそきちんと謝ろう。恵子はそう思った。