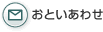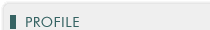志賀泉の「新明解国語辞典小説」
ち
ちすいかふうくう
2010/04/12
ちすいかふうくう【地水火風空】
〔仏教で〕一切の物が、それから生じると考えられる、もと。五大。
萌え系アニメ『にゃんこ親衛隊』DVD全四巻をTSUTAYAで借り、十二話すべてを徹夜で鑑賞しようと中村君と二人がんばって起きていたのだが、深夜になると睡魔に負けて意識が覚束ぬ。午前二時を過ぎた頃から中村君の様子がおかしくなり、背中が丸まり頭を垂れたかと思うと、なにやらぶつぶつ呟きだした。寝言?
短いフレーズをリフレインしているらしく、御経か呪文のようでもあり、なんだこいつ薄気味わりいと少し退いた目で眺めていると、中村君の身体がすうっと薄くなったのである。あれ、かすみ目? と目をしばたたいている間にもどんどん透けていき、中村君の背後にある壁のポスター、いつぞや駅の壁から引き剥がしてきたハワイのワイキキビーチが見えてきたので驚き慌て、「おい!」とテーブルを叩いた。皿の落花生が跳ね上がった。
目覚めと同時に中村君の身体は元に戻ったが、本人は自身の変化にまるで自覚がない様子で「あれ、俺いま寝てた?」と寝ぼけたことを口にする。
「寝てたもなにもお前――」
「あ、あれ? これどうなったんすか? チャッピィは無事? どうやってバーミーをやっつけたんすか?」
チャッピィとはアニメの主人公で、外見はいたいけな幼女だが内面は成熟した十九歳、実は人間に恋した雌猫の変身であり、バーミーとは彼女に敵対する黒猫一族の姫なのだがこの際それはどうでもよく、問題はおかしな寝言を呟きながら透けていった中村君の身体である。いったい何事が起きたのだろう。かような現象をどう相手に伝えればよいのか見当もつかず、阿呆のように口をぱくぱくさせている僕をよそに中村君は「くそう、いいところで寝てしまったあ」と髪を掻きむしって嘆く。自分を叱る。そんなに見たいなら早戻し機能を使えばいいのにそれは失念しているらしく、見落とした部分の解説を僕に求めるので気を取り直して細部に渡り説明してやると、中村君はいちいち「うわあ」とか「ほええ」とか過剰なリアクションで応えた。
そうしている間にも中村君ちの六畳ひと間にエンディングテーマのふぬけた女性コーラスが流れる。
にゃんぽこにゃかにゃかにゃにゃんですぽーん
にゃんちぽにゃかにゃかにゃにゃんでぴーす
――二人とも三十一歳の春である。
中村君は昨日までモンゴル人民共和国にいた。ウランバートルの裁縫工場で現地採用の女工達に電動ミシンやレーザー加工機の操作法や「LEVI'S」と「LEVI'Z」の違い、朝青龍の非道、正しいドラえもんの描き方など指導していたが、政情不安によって工場は一時閉鎖、中村君も急遽帰国し、「久しぶりに会いましょうよ」と僕に電話をかけてきたのだった。中村君は僕と同じ歳だが会社では僕のほうが先輩なので敬語を使う。常識をわきまえた社会人である。
一年ぶりに会う中村君は毛皮の帽子をかぶり、少し太っていた。特に頬肉が。体型も面貌もモンゴル人に似てきたという印象を抱いたが、考えてみれば僕はお相撲さんと成吉思(ジンギス)汗(カン)以外のモンゴル人を知らないので確かなことは言えない。それに、中村君は以前からこんなふうだった気もする。
TVによればウランバートルでは暴徒と化した民衆が市街を破壊しまくり、これを鎮圧すべく出動した武装軍隊が無差別発砲したものだから火に油、事態はますます混乱し多くの死体が道端にうっちゃられている状況らしいが、報道管制が厳しくてメディアにいまひとつ信用性がない。「市民は落ち着きを取り戻しています」と語る女性記者の後ろで兵士が市民を銃床で殴り倒し血みどろにしている始末であった。
中村君からリアルな証言を聞けるものと期待して電車に乗り一時間半かけて会いに行ったが、中村君は「はっ、あんなのどうってことないっすよ」さらに「日本のだんじり祭のほうがすごいっすよ」と涼しい顔。現地の視線というものは案外こんなふうに醒めたもので、これこそがリアルというものかもしれぬ。「それよかラーメン喰いに行きましょ」と先に立って歩く中村君のあとを、僕は腑に落ちぬ思いでついていった。
ラーメン屋でもモンゴルの治安情勢についてひと言も出なかった。代わりに話題になったのはジャパニーズ・アニメーションで、「日本じゃ『にゃんこ親衛隊』が大人気なんですってね」と箸を割った。人気もなにも、そんなアニメ僕は聞いたこともない。
「いや、寡聞(かぶん)にして知らないのだが」正直に答えた。
「うそお、本当っすか。先輩遅れてますね。モンゴルじゃいま話題沸騰っすよ」
異国暮らしの人間に流行遅れを指摘されても、いまひとつピンとこない。
モンゴルといえど地の果てというわけではなく、情報化国際化が進んだ現代においてはインターネットで日本の情報はどんどん流入する。しかし、そこはやはり社会主義を標榜する国だけあって資本主義国の頽廃文化が人民に感染せぬよう当局が目を光らせているので流入する情報にばらつきができてしまう、誤解が生じてしまう。
『にゃんこ親衛隊』にしても、どうやら深夜に放映するマニアックなアニメらしいが、画像や動画は削除され、コアなファンによる文字情報に触れるしかないから、結果、日本中で大人気という誤解を生み出したに違いなかった。
『にゃんこ親衛隊』というのは、チャッピィという名の雌猫が狂犬に襲われ間一髪のところをツトム君という大学生に助けられて恋に落ち、人間の女性に変身して彼と結ばれたいという切なる願いを抱き、それを聞き入れた猫界の魔女が未熟者だったため成熟した娘になるはずが幼女の姿になってしまい、しかもやり直しが利かない。仕方なく幼女の姿でツトム君を誘惑しようとしても巨乳好きのツトム君に軽くあしらわれ、せいぜい妹扱いされるのがオチ、というラブ・コメ物だが、ツトム君が実は病的に猫嫌いであり、なぜかといえば前世からの因縁が絡むのだが、同じく前世の因縁によって黒猫姫バーミーはツトム君を目の敵にし、前世の記憶など知る由もないツトム君に危機が迫る。チャッピィはバーミーからツトム君を守ろうと「親衛隊」を名乗り―って、ああもう。うんざりしてきた。
争乱の地から帰還した男に、どうして萌え系アニメの話を延々聞かされなければならんのか。僕が喜ぶとでも思っているのかこの男は。そもそも中村君はオタクではなかった。秋葉原へ行って名物ラーメンだけ食べ満足して帰る男だった。いったいモンゴルでどんな生活をしておったのか。訝りながらラーメンの残り汁をすすり丼を置くと、丼の向こうに中村君の恵比須顔。「じゃ、さっそくTSUTAYAへDVDを借りに行きまっしょい」
「は?」
有無を言わさなかった。
にゃこにゃこにゃにゃんにゃらりっぱにゃーご
にゃこにゃこにゃにゃんにゃらちっぱふにゃあ
中村君は、いつ帰国しても困らぬようアパートを借りっぱなしにしていた。なにやら饐えたような悪臭が台所から漂うが怖くて口に出せなかった。それよりアニメ。
「して、中村君。これは児童ポルノではないのかね?」
「やだなあ先輩。偏見っすよ。ああ見えてチャッピーは十九歳なんすから」
「しかし、スカートの下からちらちら覗く白いのはパンツではないのか?」
「あれっすか。雌猫時代の地毛の模様が変化したものなんで、パンツと違います」
なるほど、物は言い様。東京都条令に抵触せぬように言い訳を用意しているわけだ。
僕が明日の労働のためひたすら睡眠している時間帯に世のオタクどもは破廉恥なアニメにうつつを抜かしていたのかと腹立ちを抑えてビールを飲み、ポッキーをつまみつつ鑑賞していたが、第四話で不覚にも僕は涙をこぼした。感涙した。幼女趣味の頽廃的なアニメというのは誤解だった。これは悲恋と自己犠牲の物語であった。チャッピィは愛する者のために何度も何度も戦い傷つき、その愛は決して報われることがない。しかも刮目すべきは第六話において猫界の魔女がチャッピィに与えたマジカルリップの威力であり、それがゆえにチャッピィは戦闘能力に優れセクシィボディも兼ね備えたミラクルキャットへの変身を可能にしたのである。つまりだ、このアニメはロリ系オタクを満足させるばかりでなく、巨乳好きの健全な男性をも虜(とりこ)にすることに成功していた。後者に属する僕は偏見を捨て大いに安心してアニメの世界に耽溺したのであった。
しかし零時を過ぎれば日頃蓄積した労働の疲れが身体の底からにじみ出る。眠気との格闘。自分を叱咤する。励まし合う。ところが中村君は全ストーリーを熟知しているのだから僕と違って新鮮な驚きがない。眠気も太るというもの。そうして午前二時過ぎ、ぶつぶつ寝言を呟きながら透けていく中村君の姿を、僕は目撃するに至った。
当初の予測ではとっくに全十二話を観終わってしかるべき時間。しかしDVDには特典映像というオマケが付きものであり、それも併せて鑑賞したため想定外の時間を費やした。
物語はいよいよ佳境に入りツトム君の前世が明らかにされた。前世の因縁から彼を解き放ち安寧の日をもたらすためにはチャッピィが次元を越えてツトム君の前世に入り込み猫界の魔王と対決するしかない。しかしそれは猫界の摂理に背くことであり、たとえ魔王に勝利したとしてもチャッピィは元の世界に戻れない。究極の選択を迫られてチャッピィは懊悩し、ラブ・コメで始まった物語は猫界を揺るがす壮大な物語に発展していた。
にゃんちゃかにゃんちゃかにゃかにゃかにゃんにゃん
にゃんちゃかにゃんちゃかマジカルリップでにゃんぴょろぴょーん
中村君透明化の謎はほったらかしにしたまま時間は進み、第十話の途中で中村君を再び睡魔が襲った。意識が朦朧とするのか上体を前後に揺らし、薄目は開けているがよく見れば瞳は目蓋の裏に隠れ、白目だけある。「こわっ」と思ったとたん中村君はかくんと頭を垂らし、先刻と同様になにやら寝言を呟き始めた。
中村君の身体が透けてくる。衣服が先、肉体が先といった区別はなしに、まず色彩が薄れていき、全体に青みがかり、明るくなるようでもあり、骨も内臓も血管も最初からなかったように、透けていく皮膚の向こうにうっすら背景が浮かんでくる。
透明化していく、というか、物が実体を失っていく。消滅していくようでもある。分子とか電子とかよくわからんが、量子物理のレベルでなにかが起きている気がする。
なにか? なにかってなにが? なにかってなにがってなにが?
僕は中村君の口元に耳を寄せ、洩れてくる寝言の呟きを聞き取ろうとした。
――ちすいかふうくう ちすいかふうくう ちすいかふうくう
そう繰り返していた。呪文だろうか。しかしなぜ?
そうしている間にも中村君の身体はますます薄れていき、その背後からワイキキビーチの蒼い海が浮き出してくる。
揺り動かそうとして、ためらった。消えかかっている中村君に触れたら最後、一瞬に消滅してしまう予感があった。
「おい!」テーブルを叩いた。中村君はびくんと肩を震わせて目を開け、とたんに実体を取り戻し「あ、また寝ちゃった。まっじぃ」と脳天気な声を上げた。
「おい中村、お前いま、変な夢見なかったか?」僕は問うた。
「いや、なにも」中村君はきょとんとしてる。「俺、なんかしました?」
「寝言言ってたぞ」
「なんかやばいこと言ってました?」
「あのな。いや、なんでもない。もう寝るなよ。いいから寝るな」
「なんだよ先輩、おっかない顔しちゃって。悪かったよ、もう寝ねーよ」
中村君はなにも知らぬままアニメに向き直る。もう寝ねえぞと自分を叱咤し固く腕組みしたが、その目蓋はすでに垂れかけている。
僕はアニメどころではなかった。眠気覚ましにお茶でも淹れてやろうと台所に立ち急須の蓋を開けたら、いつから入れっぱなしなのだろう、腐敗したお茶っ葉に猛烈な黴が繁殖し臭気を放っている。インスタントコーヒーの瓶を手にすればコーヒーの粉末にチャバネゴキブリの死体がある。冷蔵庫は怖くて開けられぬ。
「コンビニで飲み物買ってこようかあ」
言いながらふり返ると、中村君は早くも消えかかっていた。
――ちすいかふうくう ちすいかふうくう ちすいかふうくう
重い呟き。寝言は次第にはっきりしてきた。呟きと共に中村君の内部のなにかが抜けていくらしかった。
「地水火風空」不意に思い当たった。地水火風空。しかしなぜ、このような仏教用語が中村君の口から漏れ出てくるのか。
「おい!」テーブルを叩く。激しく叩く。「お前、地水火風空って知ってるか?」
「なんすかそれ? 知らんすよ」
中村君はもう目覚めようとせぬ。それどころか不機嫌の露骨な表情で僕をひと睨みし、軽く肩を揺すって目を閉じる。もう二度と睡眠の邪魔をされたくないという固い意思が全身にありありとしている。その全身から色彩が抜けていく。
――地水火風空 地水火風空 地水火風空
僕の意識も朦朧としてくる。疲れた。だるい。眠い。
中村君が消えていくのか、僕自身が消えていくのかも判然とせぬ。知らん。どうにでもなれ。
アニメは最終回を迎えていた。ぼろぼろになった衣服をまといかろうじて裸体を隠しながらチャッピィが夕暮れの街を駆けていた。元の世界に戻れたらしい。ふり返るツトム君の胸に飛び込むチャッピィ。試練を乗り越え彼女は幸福をつかんだのだった。
どうでもいいけど。にゃかにゃんにゃん。